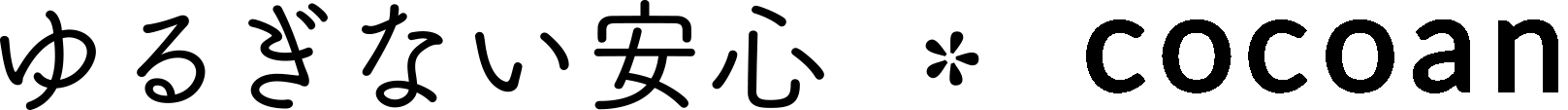HSC(感受性の高い子ども)とは
とは_LT.jpg)
HSC尺度について
HSC(Highly Sensitive Child)とは、日本語訳で“ひといちばい敏感な子ども”と説明されています。
「HSPの子ども版」と捉える方がとても多いですが、HSCかどうかをチェックする尺度は、HSP尺度とはまったく別になります。
親が自分の子どもを観察する際に、表出している動作を言葉にしています。
例えば「すぐにびっくりする」「静かな遊びが好き」などです。
アーロン博士の心理統計をもとに出した尺度の詳細は、下記リンクからご覧いただけます。
HSCセルフテスト
http://hspjk.life.coocan.jp/selftest-hsc.html
HSC尺度は、40人の親と面接をして得られた情報をもとに、60の質問項目を選出し、約100名の親から得た回答から尺度化しています。
心理学統計的に信頼性が得られている状況とはいえないことに留意する必要があります。
日本におけるHSC研究では、日本語版HSC尺度が出ていますが、論文で発表されているのみで一般的には出回っていない状況です。
現在インターネット上で確認できる信頼性のある尺度は、上記のアーロン博士の尺度のみとなります。
現場に即したHSCへのアプローチについては、“パッピー子育てアドバイザー”を開発した、明橋大二先生が先駆者となります。
著書も多数出版しており、感受性の高い子どもの子育てのヒントを多く発信いただいています。
明橋大二(あけはし だいじ)医師
https://www.shinseikai.jp/doctor/detail0031.html
クリニック臨床におけるHSC相談
クリニックHSP外来では、18歳以上の方をメインに対話をしている関係で、HSC相談における臨床件数は少ないです。
ですが、HSCを育てる親御さんからのご相談を多数受けていますので、いくつかの傾向について紹介します。
癇癪(かんしゃく)を頻繁に起こしてしまう
些細な出来事ひとつ、思い通りいかないことがあると癇癪が起こる。
そんなご相談が多いです。それは、自分の気持ちや考えを上手く言葉にできないからです。
大人であれば、自分の感情に気づき自分で処理する術を身につけています。
HSP外来へいらっしゃる親は、自身がHSPであることが大半です。
癇癪を起こす子どもへの対応に困る。癇癪を起こす背景もよくわかるので自身も胸を痛める、ということが起こります。
癇癪が起こるずっと前から、様々なストレスを受けている。
蓄積したものが爆発したもの、それが癇癪であると考えると対策がしやすくなります。
その場で出ている癇癪を抑えようとなだめる行動ばかりしがちですが、その前に「思い通りいかなくてつらいね」ということを一緒に受け止めていくことが大切です。
直面している辛さを一緒に受け止めてくれることによって、安心感が醸成されます。
心身ともに緩んではじめて、自分の気持ちや意思を明確にすることができるようになります。
「自分はこうしたい! こう思ってるんだ!」と言葉にできれば、癇癪を起こす必要がなくなっていきます。
クラスや部活の人間関係に悩む
意見を求められても言えない。
意見を言いたいけれど周りの空気を読んで言わないようにしている。
小さな積み重ねが、コミュニケーション不和を起こしていく。
結果的に関わりを断つという相談も多いです。
本当は仲良くしたいし、部活に打ち込みたい。
でも特定の人間関係を理由に辞めざるを得ない。
葛藤の頻度が多くなるのがHSCであると考えています。
HSCの葛藤に触れる親は、実際にどう声がけをしたら良いのでしょうか?
親が子どもの代わりに行動することはできません。
子どもの本音や欲求を誰よりも近くで受け止めて“味方でいる姿勢”が大切になっていきます。
声がけよりも前に、「どんな時でも隣にいる・味方でいる」ことを示すことです。
一緒にゆるめる協働調整
神経学に「協働調整」という言葉があります。
親が穏やかで余裕がある状態だと、一緒にいる子どもも穏やかになっていく。
神経のたかぶりを落ち着かせていくことになります。
学校という場所は、子どもにとって初めての外部社会になります。
そこで何が起こるかは予測しきれません。
何かあったときに戻って癒す場所がある。これが「安全基地」です。
家がその場所になるのはもちろんですが、子どもの身体の内側にも安全基地が醸成されることも大切です。
安全基地の醸成の入り口が、協働調整になります。
cocoanやクリニックのHSP外来では、まずは親であるクライエントが心身ともにゆるみ、神経が落ち着く体感を得るようにトレーニングしています。
体感できたら家庭に持ち帰って、子どもと一緒に過ごす。
時間はかかりますが、子どもの人間関係の改善に向かっていく最短ルートとなります。
学校に行きたくても行けない
気持ちは学校に行きたい。
でも、朝起きた瞬間に体が鉛のように重い。
頭痛や腹痛などの身体反応に出る。
過去の嫌な場面が夢に出てきたり、起きた瞬間に想起されたりする。
そんな様々な要因で学校に行けなくなるケースが増えています。
その頻度が増えると、周囲からは「不登校」であるとレッテルを貼られ、特別な支援の対象となっていきます。
物理的に学校に行けないと、友達や先生との関わりが減っていくので、心の距離感も大きくなります。
気持ちと身体のギャップが大きくなると、葛藤も大きくなります。
そんな姿を見ている親は、「代わってあげたい、どうにかしたい」と考える傾向にあります。
特にクリニックへいらっしゃる親は、細やかな背景まで知ろうとし、子どもの些細な気持ちの変化にも気づくので、自分で動いた方が早いと思う傾向にあります。
学校関係者と密にコンタクトを取ったり、インターネットで検索して実践を繰り返したり、どうにか解決に向かうように苦心していきます。
来院時はそんな行動に疲れ果てて、子どもも親も共倒れの状態なのです。
親にできることは沢山ありますが、子どもが何を求めているのかに添わないと、その行動は無駄に終わってしまうのです。
「学校にいく」ことが目的ではないはずです。
なぜ学校に行きたいのか? を明確にすることがはじめに必要となります。
考えられる状態になるまでは、休養、気分転換、刺激から離れる行動も大切です。
子どもだけでなく、親も同様です。
親が余裕を持って穏やかでいられると、その様子を見た子どもも力が抜けていきます。
「そっか、焦らなくていいんだ」という安心を感じられることが、本来向かっていきたい道へ進む近道になります。
「学校に行きたい」という言葉の奥に、どんな理想や欲求、思いがあるのか。
それを親子で一緒に考え言語化していく。
そんな過程をcocoanやHSP外来では提供しています。
HSCへの支援
今までに、栃木県宇都宮市、埼玉県上尾市・川越市、神奈川県川崎市の各教育委員会主催・後援のイベントにて講師をしてきました。
クリニック臨床事例を活かし、感受性の高い子どもへの支援についての提案をしています。
教育領域である、教師・特別支援コーディネーター・教育委員会担当の方々などへ講演を行い、間接的に子供達への支援も行っています(詳細は下記ブログ参照)。
子どもへの支援
https://bit.ly/44HnlyH
子どもへの支援の入り口は、まず大人である我々が穏やかでいること。
そんなメッセージを各講座でお伝えしました。
ご感想や反響がとても大きく、実際に問題解決に向かっていくきっかけになったというお声もいただいています。
cocoanでは、クリニックHSP外来での臨床と解決事例を活かし、講演や講座も承っています。
講演や講座のご要望は、下記よりお問い合わせください。
https://lifecoredesign.com/cca/request/