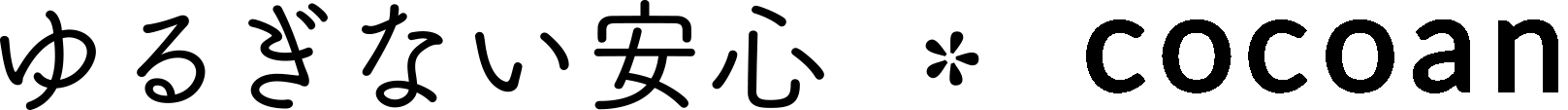HSP(感受性の高い人)とは
とは_01_LT.jpg)
HSP概念を正しく知る
もしあなたが、
- 他の人がふつうにしていることでも、私は疲れる
- 自分でコントロールできないくらい感情が爆発する
- ちょっとしたことが気になって集中できない
- 当たり前のように起こっていない先のことを予測している
そんな悩みがあるとしたら、感受性が高いかもしれません。
2020年の夏ごろから日本では、HSPブームが起きました。
「世界一受けたい授業」という番組で、HSPが取り上げられてからです。
ロンドンハーツの田村淳さんが、武田ゆきさんのカウンセリングを受けられていました。
そこで「HSS型HSP」という話題がのぼり、その話をX(Twitter)上で話したところからまたたく間に、HSPの概念が広まっていきました。
テレビ番組、新聞などのメディア、SNSなどで、HSPということを初めて知る方が急速に増えてきたのが、2020年になります。
HSPは気質的概念
HSP概念についての主観的情報(生きづらさの象徴としてのHSP)が、あっという間に広がりました。
本来、HSPは心理学領域の気質的概念(生まれつき持っている人格の遺伝的、生物学的基盤を指す概念)です。
心理学統計をおこない、再現性の確認できたものが尺度になっていますが、その事実を知っている人は少ないです。
HSPは感情論ではなく身体論
HSPは、Highly Sensitive Personの頭文字をとった言葉で、アメリカの心理学者エレイン・アーロンによって提唱されました。
夫のアーサー・アーロンは「吊り橋効果(不安や恐怖などによって緊張やドキドキを感じているときに、その場に一緒にいる人に対して恋愛感情を抱きやすくなる心理効果)」を提唱した社会心理学者であり、夫婦で感受性の研究を始めました。
1996年に感覚処理感受性として、初めて世界へ論文発表されました。
医学用語(病名や診断名)ではなく、心理学領域の気質的概念となります。
気質(Temperament)とは、人間や哺乳類などの動物集団が先天的に持っている刺激などに反応する行動特性です。
心理学では、遺伝的要素として研究している領域となります。
HSP概念は100%遺伝的要素として説明しているのではなく「遺伝と環境の相互作用で感受性が決まってくる」としています。
最近では「環境感受性理論」として、
- 感覚処理感受性:
さまざまな環境刺激に対して敏感に反応する生得的な特性 - 差次感受性:
個人の感受性と環境の相互作用によって発達のパターンに差異が生じること - 生物感受性:
環境内の事象の変化や刺激に対して反応する能力、または興奮しやすい性質
など、さまざまな感受性理論を統合して研究されています。
環境感受性理論では、良くも悪くも環境の影響を受けやすい感受性が高い人(全人口上位20〜30%の人たち)を便宜上HSPとラベルする「ニュートラルな名称」として位置づけています。
ポジティブおよびネガティブな環境に対する処理や知覚をする能力のちがいをはかります。
環境感受性理論も心理学領域としての研究であり、正規分布に基づくとしています。
- 感受性が高い人:30%
- 感受性が中程度の人:40%
- 感受性の低い人:30%
といった左右対称な山を示す分布です。
感受性の高い人の比率と、低い人の比率は同じということになります。
環境感受性を測定する方法は、心理尺度だけでなく、神経生理的な反応(脳神経の活性化領域の測定)を参照することもあります。
脳神経の動きから感受性を測定するということから「HSP概念は身体論」と言えます。
HSPの主観的な情報が広まるにつれて「感情論(生きづらさの象徴)」として捉える人が多いです。
HSP尺度について
心理統計を行って再現性が確認された正式なチェックリストは、アーロン博士HPの27項目尺度とマイケルプルース博士の感受性尺度の2つのみです。
アーロン博士HPの27項目尺度
http://hspjk.life.coocan.jp/
マイケルプルース博士の感受性尺度
https://sensitivityresearch.com/self-tests/adult-self-test/
上記以外は、すべて主観的で「根拠のないもの」です。
日本版HSP尺度も出てきていますが、論文で発表されているのみで開示されていない状況です。
日本でHSP(環境感受性)について研究している研究者は、10名に満たない状況です。
今後の最新研究動向を追っていく必要があります。
HSP尺度には、環境感受性を構成する3つの感受性尺度が散りばめられています。
その3つとは、
- 美的感受性
- 易興奮性(えきこうふんせい)
- 低感覚閾(ていかんかくいき)
の3つです。
美的感受性は、ポジティブな感受性の部分を指し、最近では「ヴァンテージ感受性」とも言われます。
目の前にある風景や自然、趣味、芸術、音楽、映画などに触れると、美しさやワクワク感、感動を強く抱くものです。
易興奮性は、興奮のしやすさを示す「圧倒されやすさ」の尺度です。
神経学的には「神経の限界点が低い」ということになります。
周りの人たちは何も気にせずに行動しているけれども、自分だけ刺激や情報が気になって疲れ果ててしまう。
それは神経の限界点のちがいからくるものです。
周囲にとっては限界までこない刺激でも、HSPにとっては限界をはるかに超えた刺激であることが大半です。
そのために「圧倒される」頻度が高く、疲れやすいのです。
低感覚閾は、周りがまったく気にも留めない小さな刺激も、ていねいに拾って処理をしていきます。
五感の鋭さを例にすることが多いです。
光や場面、匂いや香り、味や食感、音、触覚や温度感、雰囲気や態度、直感・・・いずれかの些細な刺激を察知して自動的に反応します。
どの感覚に反応するかは人それぞれです。
HSPの傾向を示す「DOES」
環境感受性尺度は、捉えることが難しい一面があります。
アーロン博士は、HSPの傾向としてDOESという言葉で説明しています。
4つの英単語の頭文字を集めた言葉で「すべてが兼備わるのがHSPの傾向」だと説明しています。
D:神経処理が深い Depth of Processing
HSP概念の根本部分です。
ただし「HSP尺度のこのチェック項目に当てはまれば神経処理が深い」と言うことはできません。
クリニック臨床のなかでよく出てくるひとつの事例から説明をすると、人から質問されたとき、メールやチャットの返信をするとき、起きていない先の先まで予測して考えていれば、生物学的に神経処理が深いと言えます。
O:刺激への圧倒されやすさ(刺激過多)Overstimulation
先に述べた、易興奮性(興奮のしやすさを示す「圧倒されやすさ」の尺度)とイコールです。
E:情動的反応 Emotional Reactivity
感情反応が強く、共感力が高いことを示します。
人間の脳の中枢部には「扁桃体」と呼ばれる、アーモンド粒くらいの器官があります。
扁桃体は危険察知を司っており、目の前の出来事が危険だと判断すると扁桃体は活性化します。
扁桃体の活性化が「情動反応」を引き起こし、不安・恐怖・怒り・悲しみといった感情が出てきます。
脳波測定の研究において、HSPは扁桃体活性が人一倍つよいと明らかにしたのがアーロン博士です。
S:些細なことに気づく Sensitivity
先に述べた、低感覚閾(周りがまったく気にも留めない小さな刺激も、ていねいに拾って処理する五感の鋭さ)とイコールです。
* * *
上記で説明したように、HSP概念は脳神経の動きについて遺伝と環境の相互作用の観点から捉えたひとつの視点ということになります。
心理学領域では、大学生を中心とした論文がメインとなり、健常群が研究対象です。
現在も心理学統計については、健常群でないと研究が進めづらいという現状があります。
私は臨床群の方(病院やクリニックにいらっしゃる方)との対話をしており、HSP研究では未開拓の領域となります。
HSP概念は特徴を知るひとつのきっかけでしかない
「HSP=人」という認識が広がったために、人が持つひとつの性質という捉え方よりも、繊細な人であるか、繊細な人でないかと(主観的に)選別することに意識が向く傾向があります。
「私はHSPだったんだ」と思うことで安心できて救われたという人は多いですが、「私はHSPです」と固定化することの危険性も知っておいてください。
例えば、HSPは気質であって病気ではないことを知った人が、自分の子どもを「HSPだから」と医療機関から遠ざけてしまったために適切な対応が遅れる、などが実際に起きています。
病院ジプシーになって、私のもとにいらっしゃる方もいます。
お話を伺って出てくる悩みのほとんどは「人との受け止め方のちがいに苦しんでいる」ということ。
それがつづいた結果、身体症状・精神症状として出てきているということです。
HSPの情報が気軽に得られるようになった今、おなじような特徴をもつ人とのグループ意識が強くなり、繊細でない架空のグループに対する敵対心や被害者意識、あるいは孤立感を募らせるというネガティブな心理反応も起こりやすくなっています。
HSPという概念は「私はHSPだ」「あの人はHSPではない」と分断するものではなく『どんな条件が揃ったら、感受性の高さが表出するのか?』を知るきっかけでしかありません。
「HSPは人」を現すものではなく「人の中にある性質」であることを踏まえておくこと。
そして、その性質を理解して自分に合った対処をしていくことが、何より大切になります。
とは_02_LT-1024x776.jpg)