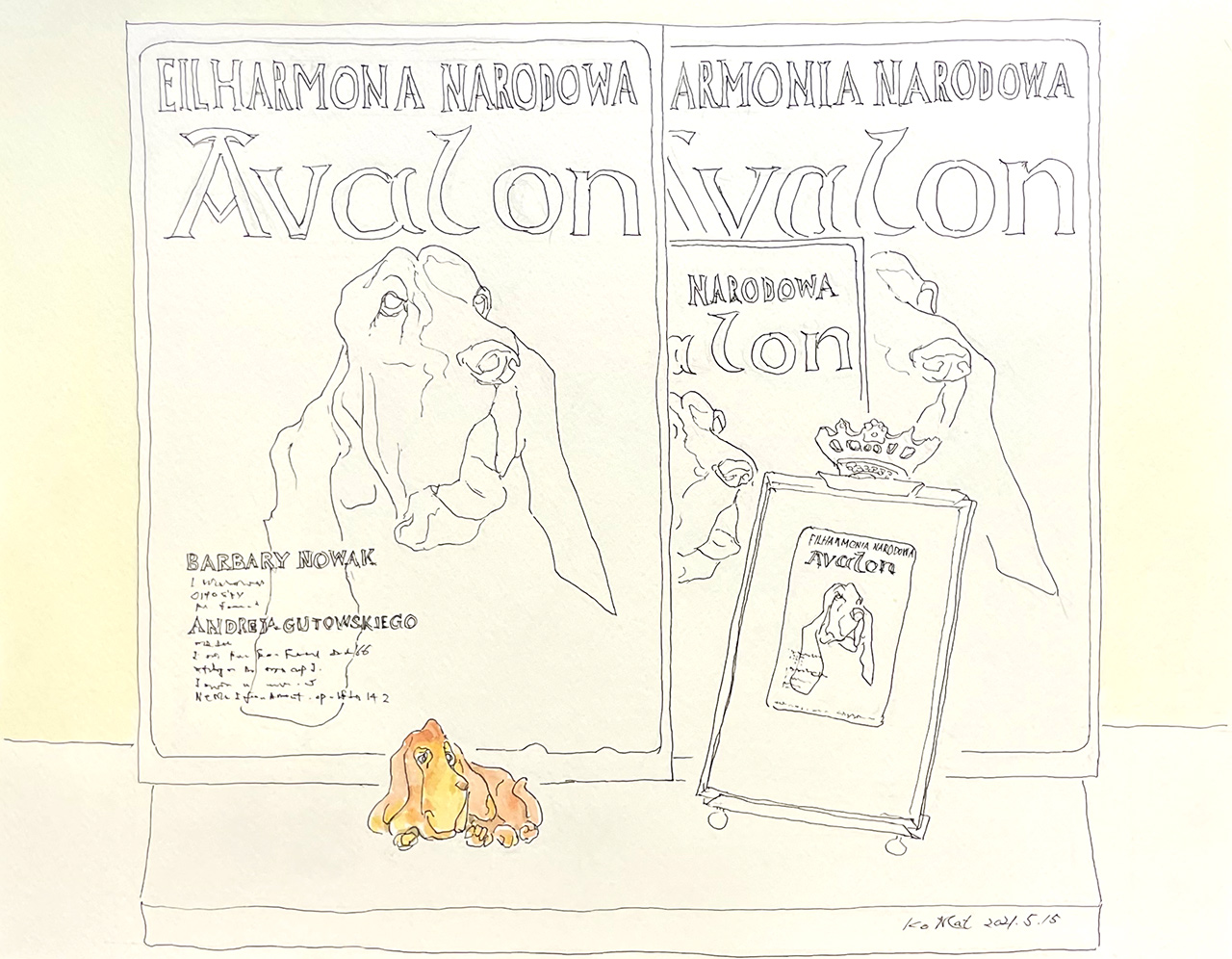原因別でみる適応障害

適応障害とは「ストレスが原因で心身のバランスが崩れ、日常生活に支障をきたす状態」を指します。
適応することが障害される、という意味なので、今いる環境に対して上手く適応できなくなっている状態ともいえます。
障害という言葉は、医療業界にて診断名として使用されることを指します。
クリニックにいらっしゃる理由のひとつとして「休職するためには、診断書をもらわないといけない」が挙げられます。
現在、私が勤めるクリニックにて、診断書で書かれることの多いものが「適応障害」となります。
下記4つの視点で、適応障害に至るまでの問題についてお伝えします。
家庭での問題
同棲や婚約・結婚によって、一人暮らしから二人暮らしに変わった。
子どもが生まれた。家族が増えた。家庭の状況が変わった。
そんな変化が起きた時に、症状として出てくるパターンです。
自分だけで過ごす分には、自分のペースを保てる安心感があると思います。
しかし、他の人が絡むことで上手くいかなくなる、ペースが乱れてストレスを抱く頻度が増えていきます。
一人の時間になった瞬間に力が抜けて一息つけても、「近くの人のために」となると過緊張がつづいていく。
家事などやることが多いけれど、疲れが溜まっていく。
疲れを無視しつづけていくと、次第に「無理して」動きつづけていくのです。
気づいたらずっと疲れてしまって、ちょっとした作業でも手がつかなくなります。
朝、自分に鞭打って起きて、家事をこなし、準備して、外に出て、予定をこなす。
その繰り返しのなかで、視野が狭くなってしまい、いつもならできることも、できなくなっていくのです。
職場での問題
- 新卒/中途入社で新しい職場に所属した
- 慣れない中で仕事を覚えることやタスク過多になる
- 職場の人間関係に悩まされる
- 望まない異動や理不尽な対応をされる
- 刺激過多な職場環境
などによって、症状が出てくるパターンです。
先のことを予測することが当たり前な人にとって「この先、何が起こるかが分からない状況」は大きなストレスになります。
前例のない新しい経験をしているときに不安になるのは自然なことです。
しかし、どうにか付いていこうと必死になっている時は、心身ともに大きな負担がかかります。
そのことに気づかないまま、周りの空気感やタスクに追われて体調を崩していきます。
周りはできているのに、自分だけできない。それが焦りになって一層がんばる。
でも空回りして上手くいかない。
周囲からの評価が下がって自己否定していく。
心配してくれる人の声も耳に入らなくなって、孤立していくのです。
自分のペースに乗っていたり、上手くいっているときは、適応できていて、環境があっているといえます。
クリニック臨床の中では、そうは感じられていない人がいらっしゃいます。
環境が良くても、タスク過多で体調を崩した方。
仕事はやりがいがあるけれど、特定の人の言動に影響を受けてしんどくなる方。
不意な異動によって今まで感じていた安心がなくなってしまった方。
職場においては、そのような方が適応障害と診断されています。
公共の場での問題
電車や人混みなどの公共の場において、刺激過多になり、不適応症状が出るパターンです。
家の中にいる分には、とくに問題はなくても、一歩外に出ようとするだけで緊張したり不安な気持ちを抱くこともあれば、特定の場面において症状が出ることもあります。
どのような相談でも共通しているのは「具体的にどの場面で刺激過多になっているのかを把握していない」ということです。
例えば、満員電車の中でパニック発作が出る場合を考えていきます。
- 知らない人と肩が触れ合って窮屈感を感じるからなのか?
- 外に出られない閉塞感を感じるからなのか?
- 電車内で聞こえる音漏れや新聞をめくる音からなのか?
発作が起こるトリガーを考える必要があります。
電車だけではなく、野球の試合・舞台・コンサートなど、人混みがとくに多い場所に行くと症状が出やすくなります。
それぞれの場面は違いますが、共通しているのは「扁桃体が目の前のことを危険だと察知している」ということです。
現実的に危険なことが起きているときは、自分の身を守る行動をすると思います。
ですが、実際は危険なことではなく、何も起きていなくても、扁桃体は危険だと察知している状態なのです。
- 人目が気になる
- 見られている感じがする
- 何かに追われている
- 攻撃されそう
そんな感覚はすべて、危険察知からくる“反応”です。
公共の場で起こる適応障害への対処は、「事実と危険だと思っている事象を切り分ける」ことです。
危険だと認識しているものが、実は危険なものではないと体感できたとき、その後の人混みに対する捉え方が変わっていきます。
新しい環境での問題
- 転職をした
- 引っ越しをした
- 入学/編入した
- 異動した
- 自分は何も変わらないけれど、周囲の体制が大きく変わった
など、新しい環境になったときには、頭で思うよりも身体に影響しています。
環境が変わる、という経験は誰しもがするものです。
経験したことのないことを味わうことは不安であることまでは自覚できても、それに対する心身の影響まで気づける人は少ないです。
世の中の8割の人たちは、目の前のことで起きたことから神経処理が始まりますが、感受性の高い人たちは、物事が起きていないときから処理が始まっています。
それを象徴するのが「予測」です。
- 嫌なことが起きたらどうしよう…
- どうなってしまうのだろう…
- 上手くできるか分からない…
- 友達ができるのか…
- 自分の選択は合っていたのだろうか…
などなど、物事が起きる前に考えているとしたら、処理が深いということです。
実際にどうなるかは、その場に身を置いてみないと分かりません。
それが頭ではわかっていても、カラダはその何倍も不安を抱いているのです。
新しい環境に身を置いたときに、慣れるまでにどれくらいの時間がかかるのかを知っておくことが大切です。
2,400件を超える私のクリニックでの対話における感覚値としては、慣れるまでに1〜2ヶ月はかかっている印象です。
1日ですべてができるようになるわけではありません。
周りがすぐに慣れて馴染んでいるのに、自分だけ置いていかれている──そう思う必要はありません。
自分には自分の慣れるペースがある。
それを自覚し、日常のなかで意識しつづけることで、環境変化に対する耐性が付いていきます。
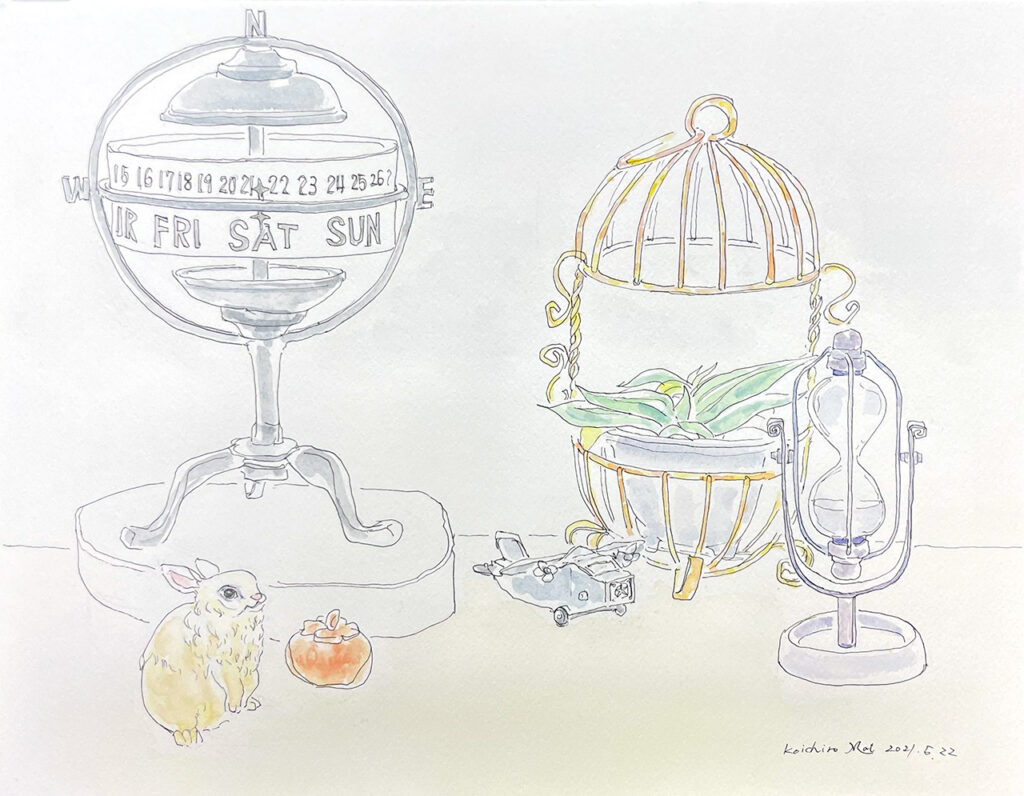
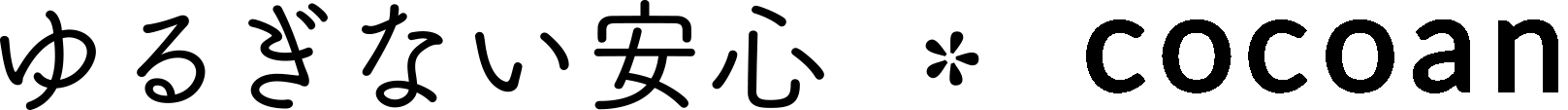

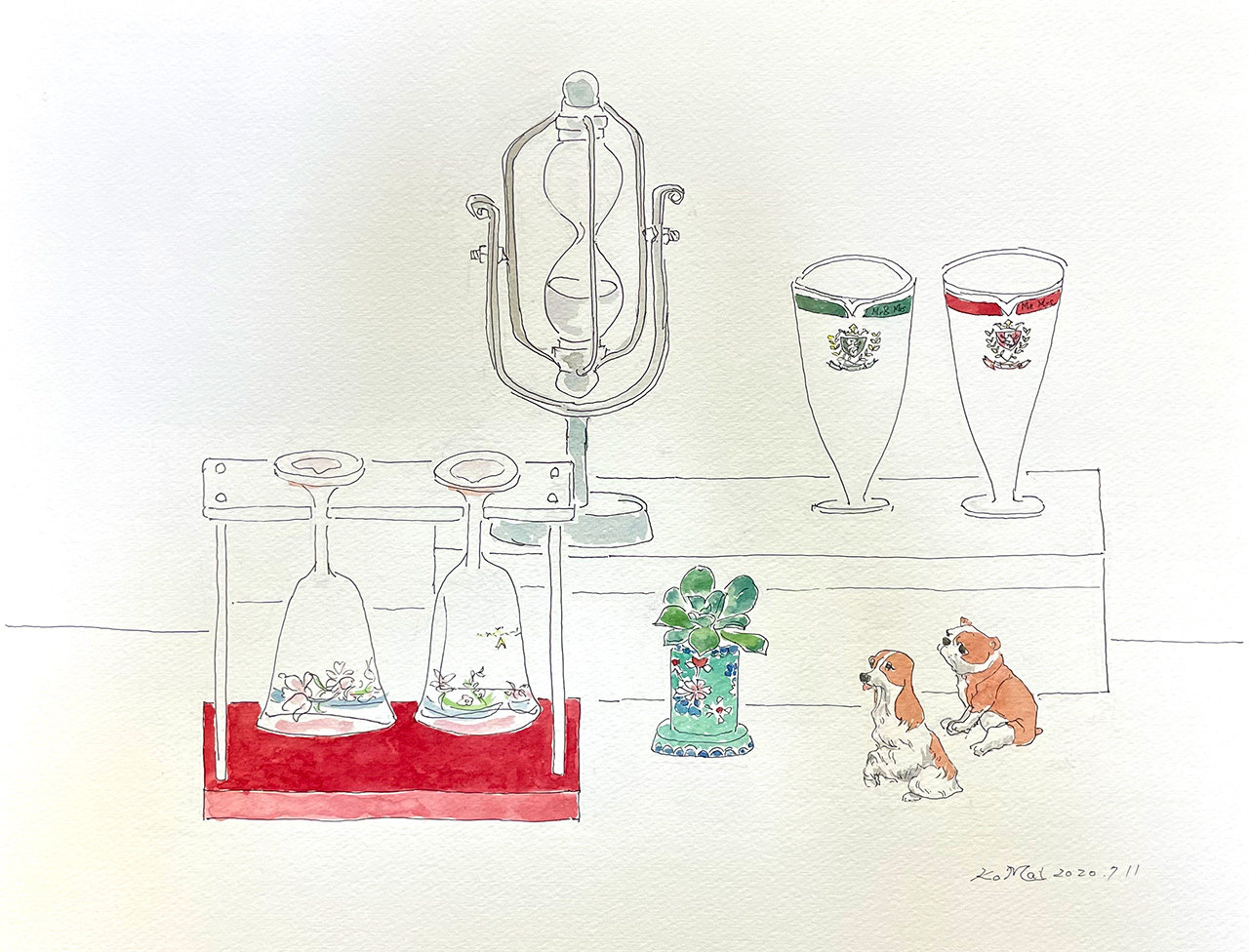
とは_LT.jpg)