HSPを受け止めてもらえない人へ

HSPを受け止めてもらえない理由
「受け止めてもらえない」とあえて表現しているのは、HSP概念自体がまだまだ浸透していないからです。
受け止めてもらえないのは、“認識の差が大きい”からです。
HSP(感受性の高い人)は、心理統計でいうと2〜3割です。
それと同じだけ感受性の低い人も存在します。
残る4割は平均的な感受性ということになります。
詳細は、Japan Sensitive Research サイトをご参照ください。
Japan Sensitive Research
https://bit.ly/4k4Y2e4
瞬時に感じ取ること
ふだん考えることや感じていることを一語一句、言葉にすることはありません。
その点は共通していても、「どのくらい深く気づいているか」の度合いは大きく変わっていきます。
例えば、職場のチームメンバーが朝会社へ出勤し、自分の席につく場面があったとします。
事実は「決められた椅子に腰掛ける」ということだけです。
感受性が高いとは、
- 出勤した人の様子に触れた瞬間から、息を切らしていること、髪がセットされていないこと、顔がほてっていること、電車が遅れるという情報がネットで出ていたし急いでいたのだなと勘繰る。
- 「おはようございます」といういつもの挨拶もなく、切羽つまった様子を感じる。
- 自分が何かしたわけでのないのに、自分ごとに捉えて「大変だったね」と声をかける。
- 表情や雰囲気から直近でどんな時間を過ごしていたのかを予測し、共に感じる。
ここまでを瞬時にこなします。
ほんのひとつの例ですが、言葉で表現するのならば、このような感じです。
認知領域の外側にあるもの
感受性の視点でいうのであれば、7〜8割の人たちは、そこまで細やかに気づくことはありません。
気づいているからこそ、思いやりの気持ちを抱けますが、気づいていない人からすると、お節介として捉えられます。
これが「どれくらい深く気づいているかの違い」となって現れます。
HSPを受け止めてもらえない理由は「気づきの深さレベルがちがう」からです。
感受性の高くない人からしたら、そもそも「気づいていない」だけなのです。
気づいていないことを唐突に言われても、理解するのに時間がかかるのは自然です。
自分が認識していないこと、関心のないことに対して、言われても受け止めることができないのです。
「私はちょっとした音が不快に感じてしまうので、やめてもらえませんか? それは私がHSPだからです」と伝えたとしても、音を出す当人がその音自体を認識していない、不快な気持ちにさせるために音を出していなければ、受け取られないのは自然なのです。
そんな認識のギャップがあることが一番、大きな理由になります。
めんどう臭がられる要素になる
認識のギャップは当然のことではありますが、とくに社会に出るとHSPであることの主張は「めんどくさい人」だと思われる要素でもあります。
決められた制約条件の中でものごとを遂行することとは、マラソンでいえば、10キロの道のりを走る時、どのペースで走って、どのタイミングで水分補給をするのかについて考えることに該当します。
走る中で、想定していないことが起こったり、横槍が入ったら集中力が切れてしまいます。
それがつづくと、うっとおしく感じるのは想像に難くないと思います。
それが仕事の中で起こったら、めんどうだと感じるのも無理はありません。
社会における現場で「私は、HSPです」と相手に主張することは、相手の流れが断ち切られるくらいのインパクトがあることなのです。
仲間を見つけにくいHSP
HSP概念は、身長・出身地・血液型のような情報とおなじように捉えられてよいものです。
でも、おなじように捉えられないのが現状です。
「地元は北海道です」とか「私はA型です」と言われたら、「そうなんですね」とか「私もそうです!」で終わります。
でも、おなじように「私はHSPです」と言っても「そうなんだね」とはなりません。
白眼視まではされずとも、「ああ、そうですか…」と、何となく冷たい空気が流れます。
それが今の社会の捉え方です。
おなじ地元、おなじ年、おなじ血液型の人と出会うと親近感が湧くように、おなじ感受性の高さをもっている同士も親近感が湧いてくるものです。
しかしながら、組織や集団のなかでは、なかなか出会うことがありません。
健常群と臨床群のはざまで
統計上では、2〜3割の人は同じような感受性の持ち主ですが、cocoanやクリニックにいらっしゃる方のほとんどは「おなじような人、分かり合える人は、0〜1人です」とおっしゃいます。
なかなか(HSPに)出会えない理由は、本当は感受性が高いけれど、隠しながら仕事をしているか、組織や特定の人の特徴を熟知して、うまく適応して仕事しているかのどちらかであると考えています。
対話の中での傾向なので、エビデンス(科学的根拠)はありません。
HSP研究はあくまでも、病院に行っていない「健常群」と呼ばれる人たちを中心に行われています。
一方、クリニックへいらっしゃる方は「臨床群」と呼ばれており、HSP研究では対象外となっています。
めんどうくさいと思われる理由は、まだまだHSPが主観的視点とエビデンス視点のはざまにあり、一般には認知の途上にあるからと考えています。
HSP概念は心理学領域なので、エビデンス視点が求められていますが、現在も研究途上の立ち位置です。
HSPを受け止めてもらえるために
自分の特性を封印した状態で組織に所属したり、働くことは、とてもしんどいことです。
HSPである自分を受け止めてもらえるためには、感受性の高くない人たちの視点を踏まえる必要があります。
意識したいことは、
- 事実だけを伝える
- I(アイ)メッセージ
- 要望は少しずつ(相手の領域に溶かす)
の3つです。
それぞれ簡単に説明します。
事実だけを伝える
めんどうくさがられる大きな理由は、感情をそのまま押し付けられるからです。
感情は大きくなるほどに受け取るエネルギー量も多くなります。
受け取る相手からすれば、しんどくなります。
感じたことではなく、「この場面の時にこんなことが起こって、この症状につながった」という事実を言葉にすることが大切です。
自分にとってはあたり前でも、相手からしたらまったく存在しない視点かもしれません。
自分が自分の状況に気づき、事実を言葉にできなければ、相手に伝わるように話すことはできません。
I(アイ)メッセージで伝える
HSPを受け止めてほしいと思っている時は、「自分のことを理解されないのは、環境や他人のせい」と受け身な姿勢が伝わります。
そう思っていなかったとしても、結果的に相手にそう伝わってしまうのは、HSP概念の曖昧性であると思います。
あくまでも、自分で感じたこと、思ったこと、起こったことは主観的です。
なので「I(アイ)メッセージ──私はこう思った」から始める必要があります。
その後に、現在いる環境や組織体系、問題だと感じる場面についての捉え方を伝える。
「私は、この状況について、こう考えています。なので、こう改善したらより働きやすくなります」という流れを踏むと、感情をぶつけることなく、自分の伝えたいことを伝えられるようになります。
要望は少しずつ
HSPであると伝えることよりも、どの条件が揃った時にどんな症状が出ていくのかを伝えることがポイントです。
一方的に伝えると、相手が受け止められなくなってしまいます。
相手が受け取ることのできる大きさのボールを投げることを意識しましょう。
無意識のうちに、相手が受け止められない大きさのボールを投げているのです。
例えば、野球ボールならすんなりキャッチできる人に、いきなりバレーボールを投げるようなものです。
自分が持つボールは、今あるボールで形容できないほどの大きさである可能性を意識することです。
現状と要望の両方が明確になれば、相手のフィールドに合わせて投げることができます。
上記の例でいえば、野球ボールの大きさにして投げるということです。
自分が気づけるレベルと、周りが求めている気づきのレベルは異なるのです。
認識の差が大きいほどに、理解されないことへのもどかしさが大きくなっていきます。
解決への道、すなわちHSPであることを受け止めてもらうためには、自分と相手双方の「気づきレベル」のちがいを理解して、相手が受け止められるレベルに分解して伝えていきましょう。

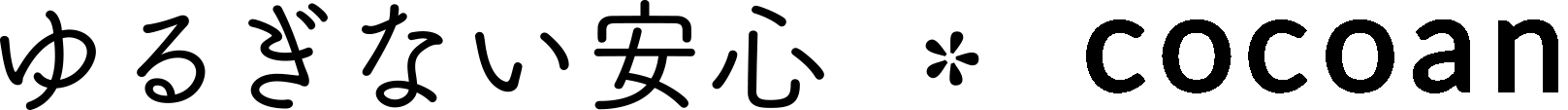

とは_LT.jpg)


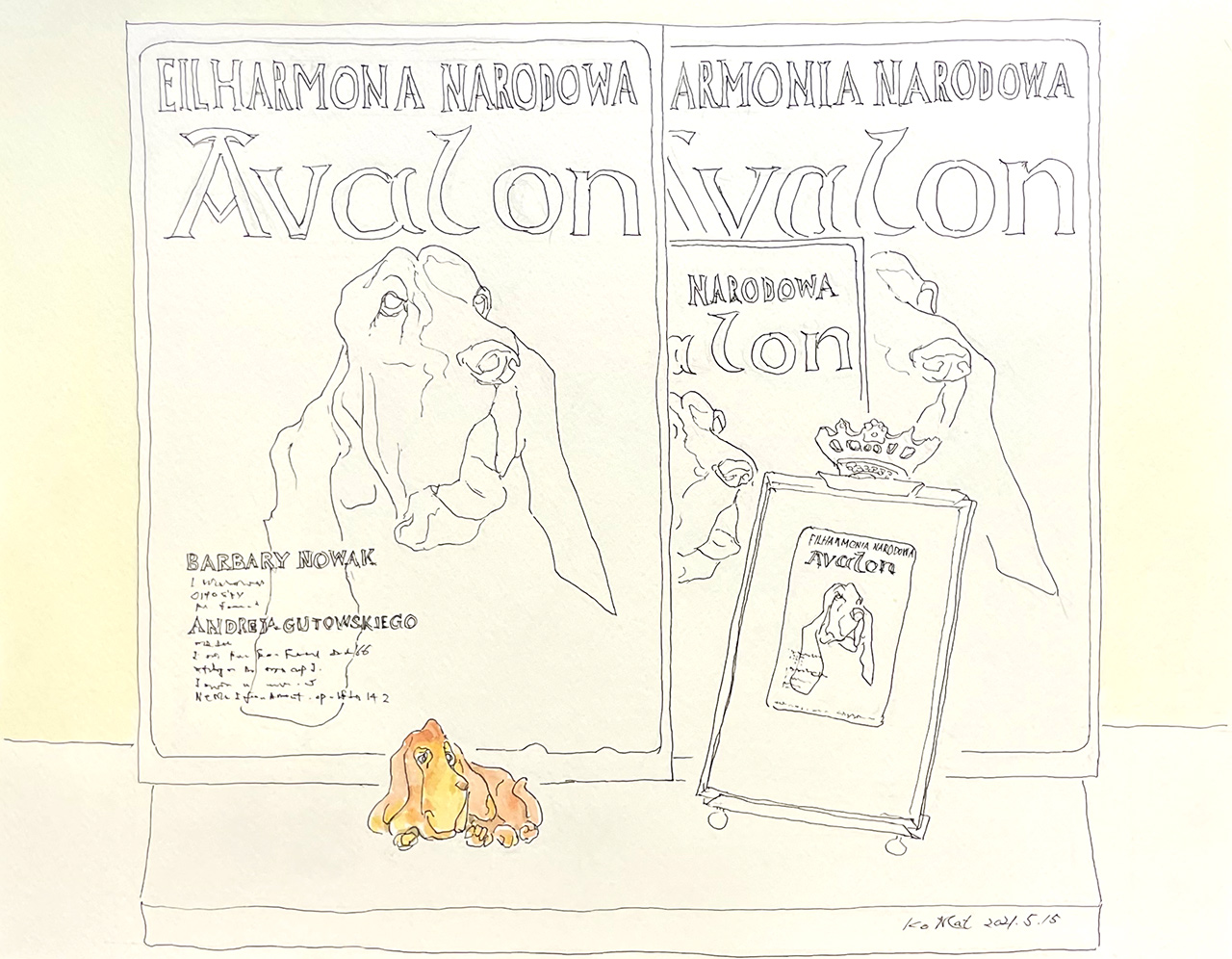

とは_01_LT.jpg)