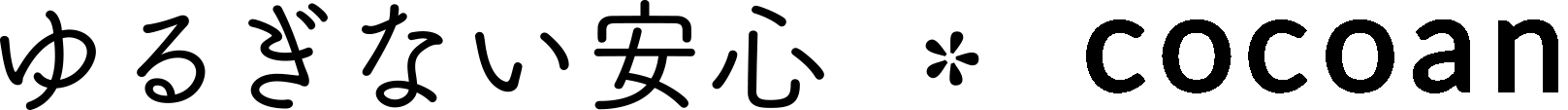HSPと発達障害のちがい

HSPと発達障害はそもそも異なる領域
HSP外来には、HSP概念と発達障害を混同している方が多く来院されます。
「私はHSPなのでしょうか? 発達障害なのでしょうか? どちらなのかはっきりさせたいんです」
そう訴えられる方の思いの強さに応えられる場所がないのが現状です。
言葉自体に囚われて、本質にまでいきつかない事態が増えていると感じています。
HSP概念も発達障害も、その言葉が生まれるまでの過程があり、その道のりは、まったくちがう領域から論じられています。
HSPと発達障害──それぞれ説明していきましょう。
HSPは気質的概念
HSPは「心理学領域」の気質的概念です。
HSP概念を提唱したエレイン・N・アーロン博士は臨床心理学者です。
現在もHSPについての研究は進んでいますが、パーソナリティ心理学・神経生理心理学・発達心理学が中心となります。
目に見えない「心」を科学するのが心理学の領域となります。
発達障害は診断名
一方、発達障害は「医療領域」の診断名・病名として使用される言葉です。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如多動症(ADHD)
- 限局性学習症(SLD)
の大きく3つのタイプに分かれます。
特性の現れ方・程度には、個人差があるのが特徴です。
ひとつの種類・特性だけが現れる人もいれば、いくつかの種類・特性が重なって現れる人もいます。
発達障害と診断されるひとつの条件として、日常生活や仕事などで支障が出ていることが挙げられます。
自分では支障が出ていないと思っていても、周囲が困っていて指摘される、というケースもあります。
医療業界で使われる診断名は、DSM−5-TR(精神疾患の診断・分類マニュアル)1や、ICD-11(国際疾病分類)2に記載されているものです。
このように、HSPと発達障害は、心理領域と医療領域とで、まったく異なる概念ですので比べることができません。
HSP概念は診断名・病名ではないので、医師からの診断はしませんし、できないのです。
ではなぜ、HSPと発達障害を混同する人が増えているのでしょうか。
HSPと発達障害の切り分け方
表出する症状や、他人から観察できる行動パターンが似ているからです。
例えば、ASD(自閉スペクトラム症)の特徴として挙げられる「感覚(刺激)の過敏さ」がHSPの特徴と一致していたり、ADHD(注意欠如多動症)の特徴のひとつである「活動に集中できない」が、HSPによく起こる刺激過多の状態では集中できないことと一致していたりすることです。
現在、日本でHSP(感受性の高さ)と神経発達症(発達障害の新名称)の関連性を示唆する研究が出てきています。
「表出する症状が類似している」という情報だけが切り取られて、SNSやWeb記事になって紹介される──そんな流れを経て混同されていくのです。
HSP外来では、脳神経の仕組みから感受性の高さを説明し、それぞれの傾向と対処についてワークします。
より具体的にいうと「冷静でいられるときに、感覚の過敏さや活動に集中できないなどの状況に至るか?」を明確にしていきます。
より詳しいHSP外来のスタンスは、下記に記載しています。
「HSP外来」担当をする理由
https://note.com/ugajin_ryo/n/nf0cbe103e64a
表出する症状が似ているとは言っても、細かく考えると「ほんの一部が重なっているだけ」なのです。
HSPや発達障害だけでなく、あらゆる言葉や概念も同じであると考えます。
例えば、マラソンと野球は、大枠「スポーツ」として捉えられますが、マラソンは道具を使わずにできる競技で、野球はボールとバットを使った競技です。
どの視座で言葉を捉えるかで、類似性となることもあれば、まったくちがうものとして捉えることもできます。
出てくる症状は一緒でも、その原因・過程・視点は異なるものです。
HSPと発達障害──視点のちがいを把握する
言葉が使われる領域が、心理学と医学でそもそもちがうという話をしました。
日ごろ、どの領域で使われる言葉なのかを意識する方は少ないと思います。
それよりも、いま自分に当てはまっていることなのか? が知りたいのではないでしょうか。
HSPは「感受性のちがい」を知るための視点で、発達障害は「脳の凹凸のちがい」を知るための視点です。
どちらも明確に目に見えるものではなく、行動や滲み出る雰囲気から観察されるものです。
脳神経の研究から導き出された言葉であるのは共通していますが、解剖するわけにはいかないので、理解がなかなかできないのです。
自分の場合は、どの環境で、どの条件が揃ったら、この症状や特徴が表出するのか?
これらを自覚するためのひとつのきっかけとして捉えると、周囲の溢れる情報に圧倒されず、自分ごととして考えやすくなっていきます。
言葉に支配されることなく、自分の特徴を言語化できるためのひとつの手段として捉えることをおすすめします。
- ※ DSM:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
5-TRとは、第5版を2022年に本文改定(TR:テキストリビジョン)されたという意味 ↩︎
※ ICD:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems最近では、発達障害のことを「神経発達症」と訳の仕方を変えています。 ↩︎