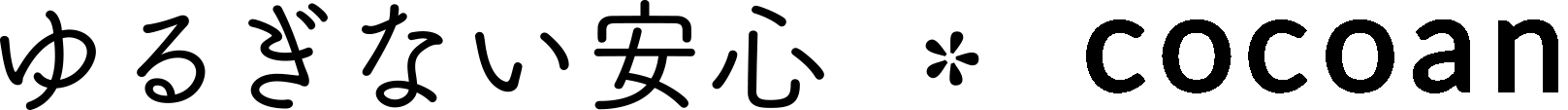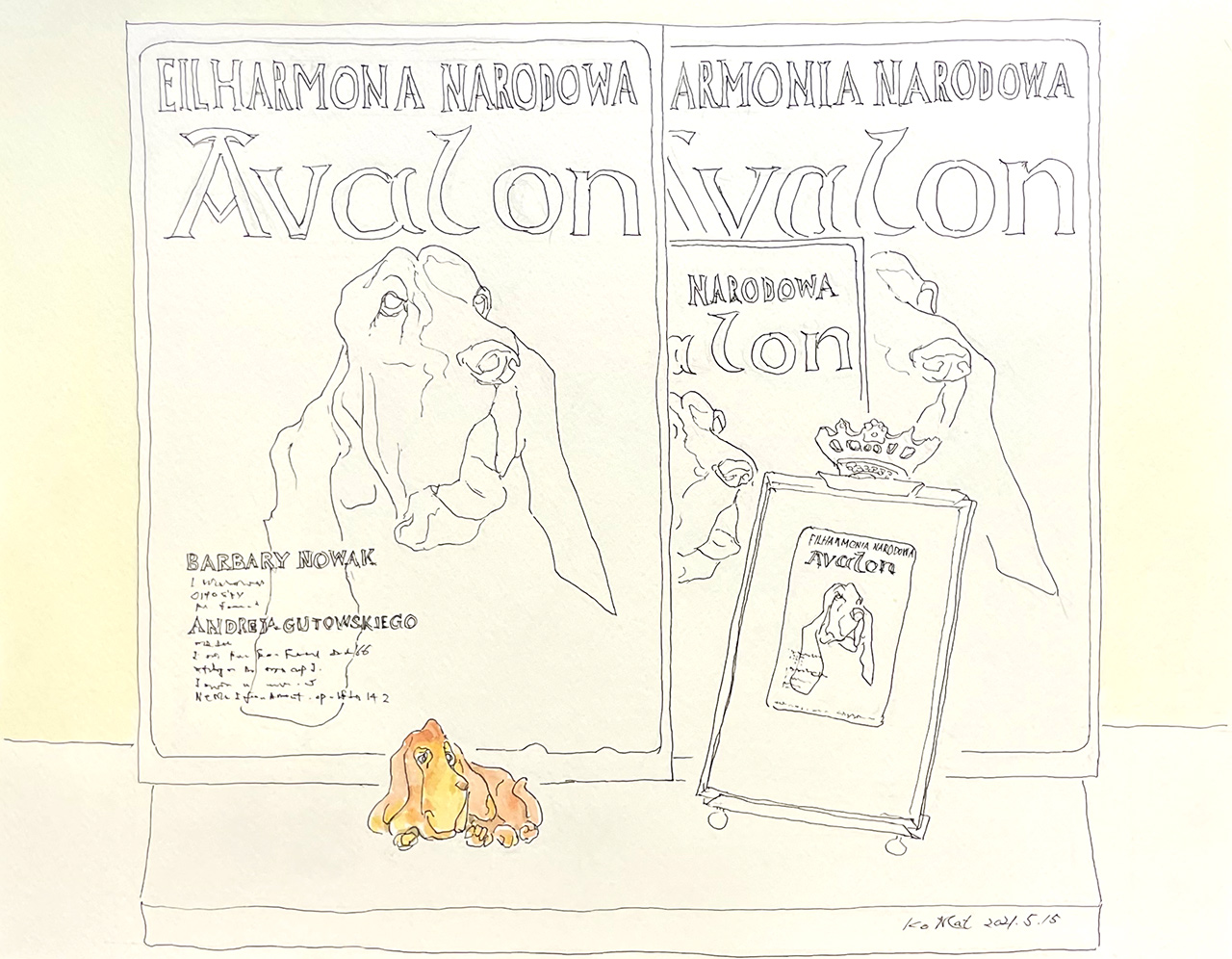HSPの部下をもつ上司へ

このページをご覧いただいているということは「私、HSPなんです」という相談を受けたことがある方、もしくは、HSPという言葉は聞いたことあるけど、実際どう対応したらいいか迷っている方、企業の管理職や集団をまとめている方々であると思います。
部下本人が表出させる反応と、HSPかどうかは、正直なところ紐付きづらいものです。
ここでは、クリニック臨床で多い事例から、どう対応したらよいかについてお伝えしていきます。
部下の沈黙の内訳
質問したことに対して、
- 15秒以上、返答がない
- 沈黙が続いてしまう
- とても困った表情をしてモゾモゾしている
そんな場面は経験されているでしょうか。
直接、遭遇するときもあれば、メールやチャットで認識することもあると思います。
どちらの場面でも、返答に時間がかかるのには仕組みがあります。
1:質問された意図を正しく捉えようとしている(もしくは掴めていない)
2:今までの経験則を思い返している
3:今できる回答の選択肢をいくつも挙げている
4:どう伝えたらいいか、あなたにきちんと伝わる言い方を考えている
5:あなたがどんな反応をするかが気になって吃っている
ざっと5つ挙げましたが、質問された瞬間にこれらのことが同時に処理されています。
部下に何が起きていて、どんなことを考えているかは、見ただけでは分からないです。
沈黙への理解を伝える
これらのことが起きていることを上司であるあなたが知っているだけで、アプローチがしやすくなっていきます。
1の場合、「そうか、そうじゃないかだけ分かればOKだよ」などと、どう答えたらいいかを示すと答えやすくなります。
2の場合、口頭時に時間が許せば「ゆっくりでいいよ」と添える。メールの場合は、いつまでに回答がほしいのかを明記しておくと良いでしょう。
3の場合、「いま思いつくもの1つでいいよ」と範囲を示すことが有効です。
4の場合、「上手く言えなくていいよ。分からないなら分からないでいいし、何となくでもOK」という言葉を伝えると、緊張や不安がほぐれて答えが得られやすくなります。
結果的に答えられない時もあるでしょう。
そんな時は、「質問したことに対して深く考えてくれてありがとう」などと、時間をかけたことに対して思いを寄せていくと良いです。
5の場合、「自分の意見を言ってしまったら、あなたに迷惑じゃないか? 否定されたらどうしよう?」と考えています。
あなたの反応を予測して怖い気持ち、不安な気持ちが出てきているということです。
「あなたの率直な意見が聞けたら良いよ。自分たちと意見がちがってもそれは貴重だよ」という言葉をかけることで、安心して回答しやすくなります。
ほんの一例を紹介しましたが、共通して言えることは「いま何が起きているのかを知る」ということです。
涙が出て話どころではないとき
本来、涙が出てくるのは、目の中に異物が入ったときか、ふかい感動や憤りが起きたとき──そう思っている人は多いです。
ですが、本人の意図と関係なく涙が出てしまうという現象が起こることを理解しておいていただきたいと思います。
職場環境の中で、たくさんの人がいる前で涙が出ている場合、本人が頭で思う以上に感情が溜まっている状況です。
まずは色んな気持ちになっていることに寄り添っていく必要があります。
「涙が出る=瞬間湯沸かし器」のように、溜まった感情が一気に爆発して吹き出している状態です。
そう認識しているだけで、動じずに済みます。
待つことの大切さ
まずはじっくりと待ち、見守ること。
時間がないことを言い訳にしたり、他のことを考えていると、感受性の高い部下はそれも察知して、心を閉ざしていくのです。
一緒の空間にいるけれど、言葉で言いくるめない。ただ見守るだけでいいのです。
本人も泣きたくて泣いているわけではないので「落ち着くまで待つ」の一択です。
落ち着いたタイミングで、何が起きていたのかを聴いていきます。
ときには本人自身、うまく言えないかもしれません。
その際は、どんな状態・環境ならやり取りがしやすいかを考えると良いでしょう。
労働環境、人間関係、タスク量、責任度合いなど、いろいろな要因が考えられます。
あなた自身も色々なことに追われているはずです。
お互いがムリすることなく、ゆったりと話せる機会をつくることが大切です。
円滑にコミュニケーションするために
HSPだと部下本人が言っていてもいなくても、自分とは感じ方がちがうのだと認識することがスタートです。
「自分ができることは、部下もできる」ではなく「自分はできると思っているけれど、実際、部下はどうだろうか?」と考えます。
認識のギャップが生まれると、コミュニケーションが取りづらくなっていきます。
認識のギャップを減らしていくための術をいくつか持っておくことが重要です。
HSPの部下が安心感を抱く会話アプローチ
例えば、納期までタスクAを終わらせてほしいときの場面で紹介します。
上司であるあなたは、タスクAを完了させるのに1時間かかると見積もっているとします。
「これやっておいて」とひとこと言うだけでは、すでに認識のギャップが生まれています。
「タスクAがあるのだけど、1時間をメドに完了できる仕事だと思ってる。いまの仕事状況からお願いすることはできる?」
と具体的に示すことで、出来るか否かを考えやすくなります。
もし長年、部下を見てきて、1時間ではムリそうだなと想定できるときは、他の人に振るか、対応できるレベルに分解して依頼すると良いでしょう。
部下の特徴がわからないときは、「1時間でできそう?」だけを訊いてみて、感触を確かめます。
それでも回答されない場合は「どの部分でつまずきそうか?」を確かめます。
本人もわからないケースもあるので“一緒に”考えることが重要です。
相手の代わりに言葉にする、相手の視点に立って話をするという姿勢を持っているだけで、HSPの部下は安心感を抱き、対応しやすくなっていきます。
社会の中では、感受性の高さを封印している人が多いのです。
効率的にスピード感をもって納期を守る。そのスタンスがあたり前な環境です。
会社の評価ポイント以外の「丁寧さ・深く考えるプロセス」に歩み寄るだけでも、円滑なコミュニケーションにつながっていきます。
気持ちを傾けてあげてほしい
感受性の高さゆえに起こっていることについて、クリニックでの臨床例からご紹介しました。
「自分は気にならないからわからない」「理解できないから困る」と目の前の部下に起きていることに対して諦めず、気持ちを傾けてあげてほしいと思います。
この記事が、HSPの部下との円滑なコミュニケーションにつながることを願っています。