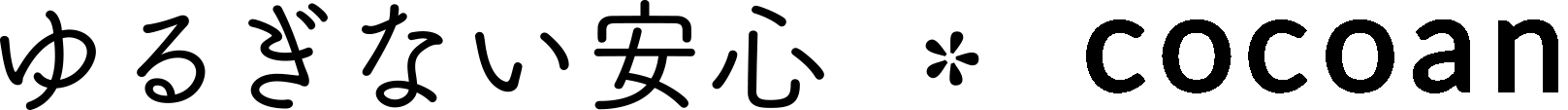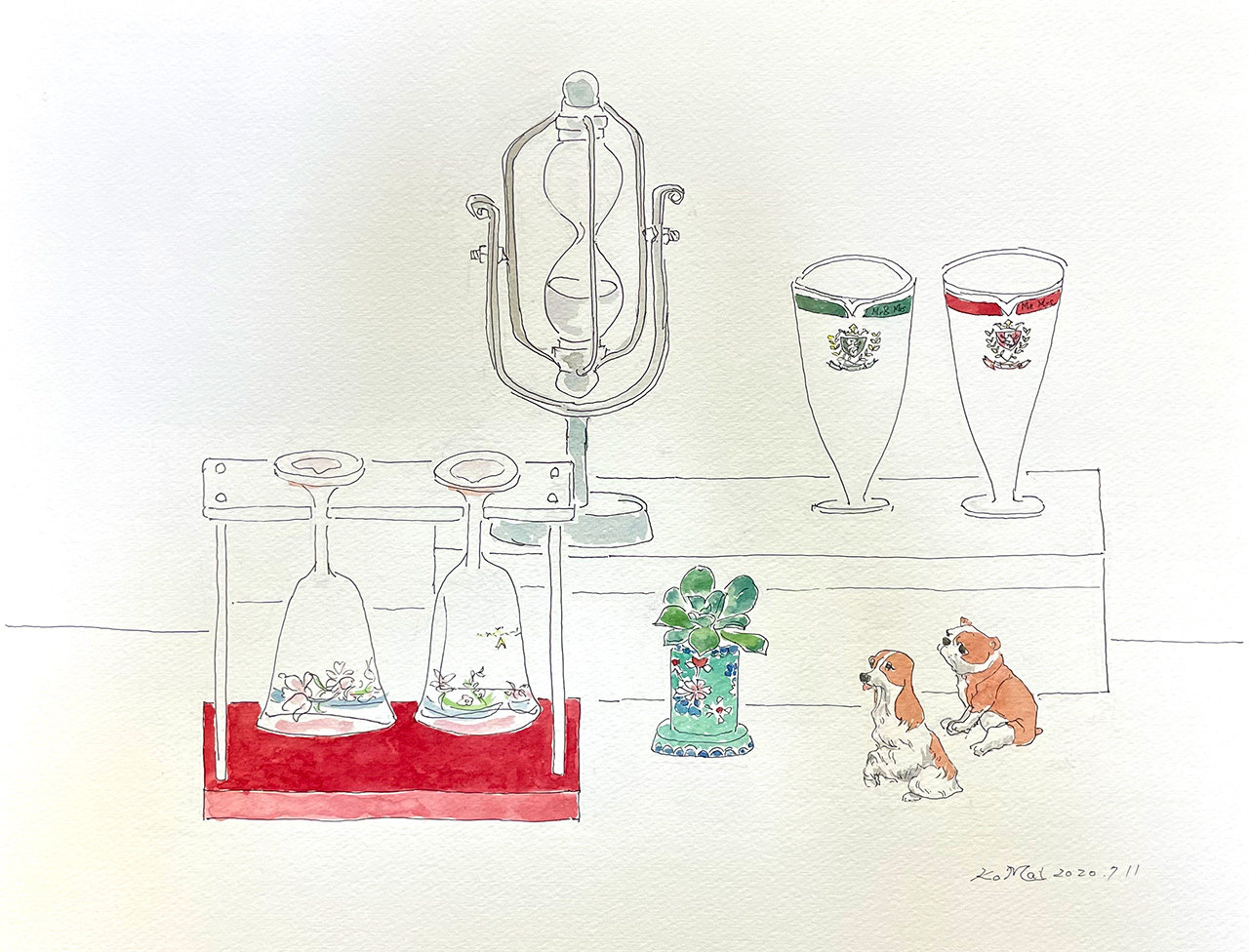神経の高止まりとHSP

自律神経の仕組み
ここでいう「神経」は自律神経のことを指します。
自律神経は“自らで律する”ので、コントロールすることができません。
生命維持に欠かせない活動である、呼吸・対応・血圧・心拍・消化などの機能を調節する役割を担っています。
自律神経は、交感神経と副交感神経に分けられると認識している方が大半です。
不適応症状を特定する神経分布
ここでは、感受性の高さゆえに不適応症状がどうして出るのか? の視点に立つために、下記のとおり、神経を4つのパターンに分けてお伝えします。
- 闘争/逃走モード(交感神経の高止まり)
- 休息/消化モード(背側迷走神経)
- 凍りつきモード(背側迷走神経)
- つながり/安心モード(腹側迷走神経)
ステファン・ポージェス博士が提唱した「ポリヴェーガル理論」という考え方にのっとっています。
ポリ(poli)は“多重の”、ヴェーガル(vagal)は“迷走神経”をさし、日本では“多重迷走神経理論”と訳されます。
副交感神経の中にもさらに2つの迷走神経に分かれるという考え方です。
物理的には脳幹から見て背中側から出ているものが「背側迷走神経」、そして、お腹側から出ているものが「腹側迷走神経」です。
4つのパターンのうち1つは交感神経の動き、2つは背側迷走神経の動き、残り1つは腹側迷走神経の動きになります。
もう一度、掲載しておきます。
- 闘争/逃走モード(交感神経の高止まり)
- 休息/消化モード(背側迷走神経)
- 凍りつきモード(背側迷走神経)
- つながり/安心モード(腹側迷走神経)
通常、交感神経は、朝起きてからの活動期に活性化していきます。
仕事や作業が終わった時には副交感神経系が優位になっていきます。
交感神経と副交感神経が活動状況に合わせて、それぞれ交互に出ていくのが通常の働きです。
闘争/逃走モード(交感神経の高止まり)
しかし、感受性の高い方はちょっとしたことで交感神経が動くので「交感神経の高止まり」というのが起きます。
それによってリラックスができなかったり、力が抜けなかったりする。
言い換えれば、副交感神経系が働かなくなってしまうのです。
交感神経の高止まりがつづくと、自律神経の本来の動きが乱れていきます。
自律神経失調症として身体症状に出てくることもあります。
交感神経は2つの“とうそう”反応を司ります。
闘う・争うと書く「闘争」と、逃げる・走ると書く「逃走」の2つです。
“とうそうモード”の具体的な身体反応は、
- 瞳孔が開く/呼吸が浅くなる
- 動悸/筋肉血管が収縮し血圧が上がる
- 肩こり首こり
- 消化機能の抑制
などがあります。
消化機能が抑えられると、ご飯を食べてもうまく消化されずに腹痛になりやすかったり、ストレスがお腹の痛みとして出てきたりします。
過敏性腸症候群(IBS:irritable bowel syndrome)と診断されるクライエントも数多くいます。
また、緊張型頭痛や偏頭痛の原因にもなります。
感受性の高い方が心身不調に陥る大きな入り口は「交感神経の高止まり」が引き起こしているのです。
副交感神経系の3パターン
副交感神経系には3パターンあり、2つは背側迷走神経の動き、残り1つは腹側迷走神経の動きになります。
休息/消化モード(背側迷走神経)
副交感神経の3パターンのうち、交感神経と逆の動きをする1パターンを「休息/消化モードの神経」といいます。
- 呼吸が深くなる
- 鼓動がゆっくりになる
- 筋肉血管が弛緩する
- 血圧が下がる
- 力が抜ける
- 消化機能が促進される
といった反応です。
例えば、ご飯を食べていて“美味しい”と感じられること、お風呂やシャワーで身体があったまり、リラックスする感覚、歯を磨いてスッキリした感覚などを指します。
凍りつきモード(背側迷走神経)
日常生活における行動自体が面倒くさく感じる場合は、交感神経が高止まっているといえます。
交感神経は、これ以上、刺激を受け取ったら無理! という限界点が存在します。
これをロシアの心理学者であるイワン・パブロフは「超限界抑制」といっています。
この神経の限界点を超えて刺激を受けつづけていくと、交感神経は働かなくなってしまい、他の神経に切り替わっていくのです。
この神経が2パターン目である「凍りつきの神経」です。
生存本能によるシャットダウン状態です。
生存戦略としての“しんだふり”
cocoanやクリニックでは、シカとライオンの例えで説明しています。
遠くの距離でライオンの姿を見かけたシカがいたとします。
シカはその瞬間、交感神経が優位になって逃走モードになります。
しかし、至近距離でライオンと遭遇してしまったとしたら、シカはどうなるでしょうか?
その場で“しんだふりの反応”が起こります。
なぜなら、ライオンがシカを見つけた時に、ピクリとも動いていなければ、腐って手をつけられないとライオンが判断し、その場から離れることがあるからです。
シカでいう“しんだふりの反応”が、凍りつきの反応なのです。
これ以上、刺激を受けると、命が危ない! と神経が判断し、シャットダウンしてくれているのです。
凍りつきは、命を守る「防衛反応」ということができます。
人間もおなじ反応が引き起こされる
人間ももちろん、凍りつきの反応が起きます。
罪悪感や恥じらいの気持ちが強くなる人もいれば、「あぁ、自分の言動であの人を嫌な気持ちにさせちゃったな」などと、自己否定ループになる人もいます。
パニック発作やうつ気分につながる人もいます。
cocoanやクリニック診療にいらっしゃる方で一番、多いのは、仕事が終わって帰宅後や休日は、やりたいことがあっても身体がついていかない、やる気の喪失、何もしたくない虚無感を感じる、というお話です。
感受性の高さゆえに、交感神経の高止まりと凍りつきの神経の切り替えが起こりやすいのです。
そのネガティブ・ループを抜けていくために大切なことは、あと1つのパターンの神経がポイントになります。
つながり/安心モード(腹側迷走神経)
3パターン目は「つながり/安心」を感じる神経です。
人とのつながり、「社会交流神経」とも言われ、哺乳類以降から育まれたとポージェス博士はいっています。
言い換えるのであれば「安心・安全基地」です。
カラダの内側に安心感が醸成されていれば、どんな環境であれ、刺激過多の状況であれ、冷静に物事を判断できるようになります。
またストレスだと捉えなくなるくらいに心身の余裕が生まれるので、受け止め方も緩んでいくのです。
制動レベルが異なる副交感神経
副交感神経系の3パターンをまとめると、休息/消化モードと社会交流神経(つながり/安心モード)の2つは「緩やかなブレーキ」、凍りつきモードは「急ブレーキ」と表現することができます。
交感神経と合わせた4つのパターンで考えると、いま表出している症状や問題の根本原因が見つけやすくなっていきます。
以下に4つのパターンを表にまとめておきましたので参考にしてください(スマホで閲覧の方は右にスクロールできます)。
| 神経モード | 自律神経の内訳 | 副交感神経系の内訳 | 脳神経の状態 | 反応属性 | カラダの状態 | 引き起こされる結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闘争/逃走 | 交感神経 | ── | 交感神経の高止まり | アクセル | ファイティングポーズ/前傾姿勢 | 血圧上昇・呼吸が浅くなる・鼓動が早くなる・消化機能抑制・腹痛/頭痛・身体硬直 |
| 休息/消化 | 副交感神経 | 背側迷走神経 | 副交感神経の正常稼働 | 緩ブレーキ | 休む/食べる | 力が抜ける/緩まる・消化機能促進・呼吸が深くなる |
| 凍りつき | 副交感神経 | 背側迷走神経 | 扁桃体症候群 | 急ブレーキ | シャットダウン/生存本能 | うつ・パニック・罪悪感・恥・やる気喪失・自己否定 |
| つながり/安心 | 副交感神経 | 腹側迷走神経 | 鰓弓神経の正常稼働 | 緩ブレーキ | 心地よさ | 自尊心形成・マインドフル・自己肯定感・受容・ちょうどいい |
安心感を醸成する
cocoan、およびクリニックでは、神経学の視点から、「悩んでいる症状」に対してではなく「根本にある原因」に着目し、お越しくださる方との対話を形成しています。
根本にある原因とは、症状や感情、反応が起こるようになった環境やトリガー(刷り込みの場面)を指します(脳神経や身体器質的な領域は、クリニックの医師が対応します)。
どのように原因に着目していくかというと、直近での場面で抱く感情や身体反応が起こる「きっかけ」に気づくことです。
身体反応や症状は、神経のどのパターンとして出るのかを知ることにつながります。
- 交感神経の高止まり状態なのか?
- 凍りついているのか?
- 休息/消化モードは働いているのか?
などをヒヤリングします。
根本原因を解決するためには「交感神経の高止まりと凍りつきのループ」から抜け出し、「休息/消化モードと社会交流神経」を育むことが大切です。
育みを積み重ねることで「安心感を醸成」することができるのです。
安心感の醸成
↓
神経の高止まりを抑える
↓
場面の受け止め方がゆるまる
↓
冷静に受け止められて、気にならなくなる
という流れを辿っていきます。
この流れが、日常の中で回るようになることを目指しています。
4年で2,400件を超える診療臨床を積み重ねる中で、HSP概念を軸とした支援がより明確化しています。
いまの社会に蔓延している“生きづらさ”に切り込む新たな視点が「神経の高止まり」であるといえます。