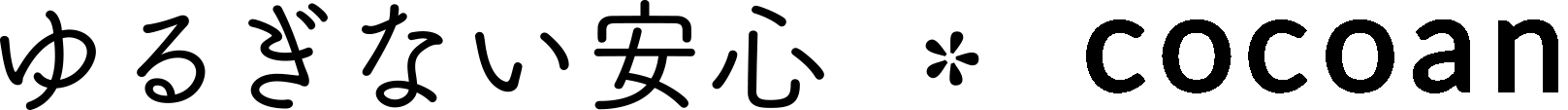内向と外向の考え方
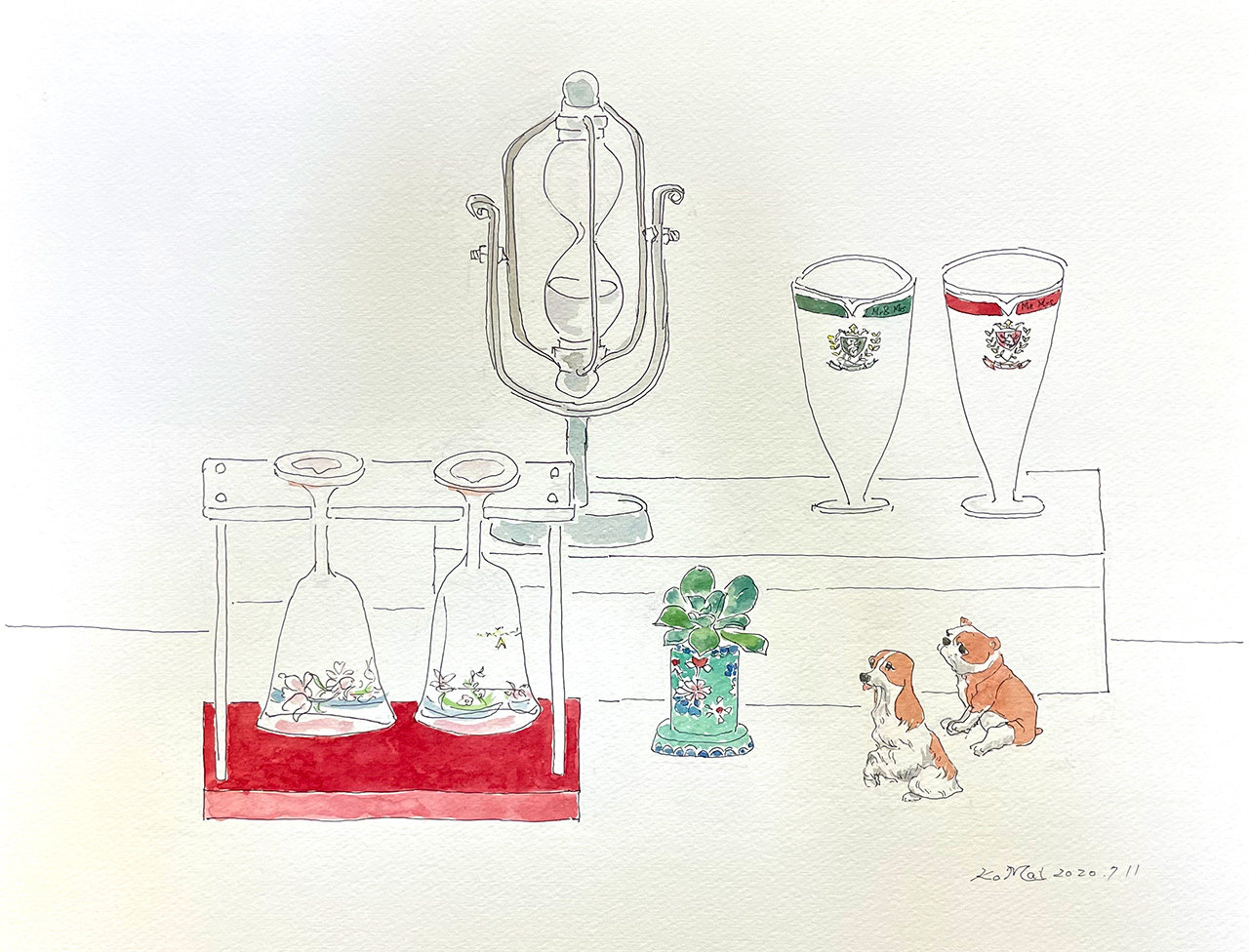
HSP概念が日本で広まった2020年。
本来は感受性の高さを示す言葉ですが「内向型HSP」「外向型HSP」と、SNSのプロフィールで名乗る方が増えて、手っ取り早く自分のことを知ってもらえる手段となっています。
そもそも内向型/外向型の考え方はどこから始まったのか?
それは、心理学者のカール・ユングが提唱している考え方に始まります。
心理学者ユングについて
1921年、スイスの精神科医であるカール・グスタフ・ユングは、心的エネルギーが自分の内側に向かうのを内向型、外の事象に向かうのを外向型と、2つの基本的態度に分類しました。
人はそれぞれ、もっとも得意とする心理機能を持っているとし、思考・感情・感覚・直観という4つの心理機能があるとしました。
このようにユングは、タイプ分類の考え方を提唱しています。
人の性格はとても複雑で一概に言えないため、大枠を定めて分類することで性格を捉えやすくするようにしました。
ユングの著書『タイプ論』の一文を紹介します。
「人間の心理反応はきわめて複雑であるから、私の説明能力をもってしては、それを見事に描ききることなどとうてい及びつかないことであろう。やむえず私は、観察されたたくさんの事例から抽出したいくつかの原理を説明するにとどめざるをえない」
タイプ論
カール・グスタフ・ユング
https://amzn.asia/d/bXaaeIh
内向・外向の基本的態度と、4つの心理機能を合わせて、1962年にマイヤーズ・ブリッグスタイプ指標(MBTI)が開発されました。
現在のSNSでも“MBTI”という言葉を知っている方が増えたように思います。
現代においても、ユングの考え方は支持されていることが分かります。
HSP概念を提唱したアーロン博士は、ユング派の心理学者と言われているため、ユングの考え方が反映されていると考えることもできます。
内向型/外向型とは?
内向型とは、心的エネルギーが内側に向いていること。
外向型は、心的エネルギーが外側に向いていることを指します。
心的エネルギーという言葉ではイメージしづらいと思いますので、例を挙げます。
内側の心的エネルギー
内側の心的エネルギーは、自分が抱く思考・感情・過去起きた出来事を思い返す・妄想に耽る・未来のことを想像することなどが挙げられます。
意識エネルギーのベクトルが自分の内側に向かっている状態です。
外側の心的エネルギー
外側の心的エネルギーは、目の前の風景や場面・人と一緒にいること自体・人の表情や雰囲気・コミュニケーションを図ること・周りに意識を向けることなどが挙げられます。
意識エネルギーのベクトルが自分の外側に向かっている状態ですね。
SNS上では、内向型は一人を好み、外向型は人との関わりが好きで自分から求める、と語られていることが多い印象です。
その認識が一人歩きし「内向型HSPは一人を好み、外向型は人との関わりが好きだけど疲れる」などと表現されるようになりました。
その表現は、本来の内向・外向の考え方から離れてしまいます。
内向/外向は二元論でみない
内向型HSP/外向型HSP(HSE:Highly Sensitive Extrobert)という言葉が日本で流行っていますが、わかりやすい反面、視点を狭めてしまうリスクがあります。
人には内向と外向の両方が備わっていて、その比率やどの条件のときにどの傾向が強いかのちがいがあるだけです。
24時間ずっと内向的ということはあり得ません。
ですが内向型と言ってしまうと、あたかも24時間内向的なタイプが発動していると誤解される可能性が大きくなってしまいます。
よく考えれば、学校に行ったり、人と話したり、外に出ること自体は、外向的でなければなし得ません。
内向型といっても外向的な要素がないということでもなければ、外向型といっても内向的な要素がないということでもありません。
- 内向型は人との関わりを避ける、自分一人でいたほうが楽
- 外向型は人との関わりが好きで、自分から話しかける、人見知りはしない
などというという投稿を見かけますが、それらは主観的であって一概に言えないのです。
内向/外向と決めつける前に
それよりも「自分がどんな状態でいると内向もしくは外向が強く出るのかを知るひとつの考え方」と捉えると、わかりやすくなります。
人は内向的な要素と外向的な要素が「波打つように連続して」起こります。
それを「連続性:スペクトラム」といいます。
一定の決まった流れがあるわけではなく、不特定な流れのままに起こるものです。
流れが不特定だと、自分自身でも理解がしづらいものです。
内向/外向と決めつける前に、具体的に「どの場面・状況なら、どちらに心的エネルギーが注がれるのか?」を考えることが大切です。