非HSPに通じる言語

同一化を認識し、手放す
敢えて「非HSP」と表現するのは、“感受性のちがいの大きさ”を認識しやすくするためです。
自分の感じること、思うことは当たり前ではない──それに気づけるだけで、相手の態度や動作に翻弄されずに済むからです。
自分が感じることは誰しも感じる。
自分ができることは、みんなできてあたり前。
この思い(期待)を手放すと、他者が感じていないという事実や、できなていないことに対してイライラしなくなります。
cocoanやクリニックにおいて多いご相談は、「自分にできることが、周りができていなくてもどかしい」ということです。
その逆に「周りはみんなできていることが、自分だけできなくてもどかしい」も同類といえます。
非HSPに通用しない言葉
こうした感受性のちがいによって、非HSPには通用しない言葉が浮き彫りになってきます。
例えば、
- 気になる
- やりたいけどできない
- 勝手に涙が出てしまう
- ちょっとしたことでびっくりする
という言葉です。
これらの言葉は、非HSPにとっては“言い訳”にしか聞こえなくなるからです。
言い訳だと捉えられる理由は、受け手にとっては「まったく、その経験がない」からです。
よくSNSの投稿を見ても、
- あれこれ考えて悩むくらいなら、動いたらいいです
- 行動したらヤル気が出る
- 細かいことを気にしすぎなだけだと思う
という内容で溢れかえっています。
感受性という視点の曖昧性
非HSPからすると、意識して「気にする」視点しか持たないので、勝手に、とか、無意識のうちに察知してしまう「気になる」という感覚がないのです。
だから「意識でコントロールすればいいのに」となります。
その度合いが人によってちがうし、計測できないのが「感受性という視点の曖昧性」になります。
非HSPが言うことは正しい。だけれどそれは万人にとっての正しさではない。そのことを踏まえる必要があります。
そもそも気づかないのだから、どれだけ非HSPに「わかってください」と言っても、伝わるはずがないのです。
非HSPには通用しない表現
本来できることが、ある理由でできなくなる。
まったくできないのであれば、HSPもできるようになるために意識を保てますが、一度でもできた経験をしているのにも関わらず、できなくなってしまったとなると、自分が許せなくなってしまう。
その流れが非HSPには到底、理解ができないのです。
だから、
- 気になる
- やりたいけどできない
- 勝手に〇〇してしまう(意識しなくても)
- ちょっとでも〇〇になる
という言葉は、非HSPには通用しないと認識しましょう。
相手の認識レベルに合わせる
では、どのようにして伝えたら良いのでしょうか?
その答えは、非HSPの認識レベルをまずは知るということです。
感受性の視点で言えば「相手はどこまで認識できるのか?」を見定めるということです。
例えば、アパートに住んでいるとします。
上層階からの足音でまったく眠れないくらいに気になる場面があるとします。
「気になってしまう」感覚はないですが、非HSPにとっては、どの程度認識しているのかを探っていきます。
- 足音の存在自体を認識していないのか
- 足音は認識しているけど気にはならないのか
- あえて気にしないようにしているのか
- 「何か作業しているのかも」と意識しているのか
その度合いはそれぞれです。
どのように認識しているかが分かった時、そのレベル感に合わせていくことができます。
足音の存在自体を認識していない人に対しては、その人がどこまでの音なら認識できるのかについて考えていきます。
職場の外で工事の音がしている様子に対して反応しているとしたら、「この音レベルは認識している」と分かります。
その音が不快であると捉えているのか、ただの音として捉えているのかも分かれます。
不快であると思っているのならば「その不快が24時間ずっと続いているような状態です」と言うことができます。
非HSPの認識レベルからみて「その状況が続いたら、そりゃしんどいよね」と納得できる状態でなければ、理解につながりません。
相手の認識レベルを知るために、その人を観察すること。
自分の感じ方と、どうちがうのか?
受け止める度合いはどうか?
について、意識を向けて見ることが大切です。
非HSPに通じる言葉の具体化
非HSPに通じる言葉とは、相手が具体的にその場面をイメージしてもらうための言葉です。
例えば、勝手に涙が出てしまって仕事に支障が出ているとしましょう。
単純に「勝手に泣いてしまうのです」だけでは、もちろん相手にとっては、その感覚がないので伝わりません。
涙が出てしまう仕組みと流れを具体的に説明することが、理解への近道になります。
例えば、10人チームの会議で、自分の意見という場面の時。
『みんなから視線を向けられると「否定されたらどうしよう」と怖い気持ちになってしまって、身体がこわばって、緊張してしまいます。
それがつづくと、もう耐えられなくなって涙が出てしまいます。
体調が良いときは、涙が出るまでではないのですが、体調が悪くて、納期に追われたタスクを3つ抱えている時には、会議室に入った瞬間から涙が出そうになります。』
──ここまで具体的に説明をすると、自分がどう感じるかとは関係なく、状況は理解できるはずです。
ただし状況を説明するだけでは、相手の行動にはつながりません。
そのため「どうしたら涙が出なくなるのか?」についても言及します。
『対策としては、納期に追われたタスクは1つに留めたいです。
体調が悪くなる要因は、納期に追われるプレッシャーが一番大きいと考えています。
体調を安定させるためには、タスク量を調整して、同僚と交渉したいです。
それができるかどうかを一緒に考えていただけませんか?』
──ここまで言えると、理解できないはずがないのです。
非HSPにとっても、具体的に自分がどうしたらいいのかについて、明確に認識できます。
具体的に言葉にするとは「自分の物語を相手が理解できるようにする」ということとも言えます。
ふだん、自分にとってあたり前の感覚や気づきをわざわざ細かく言葉にはしないと思います。
ですが、HSPにとっては、異なる認識レベルの人がイメージできるよう、具体的に言葉にするという過程を大切にすることは、あらゆる感受性のちがいを乗り越えるコミュニケーションを育むことにつながります。
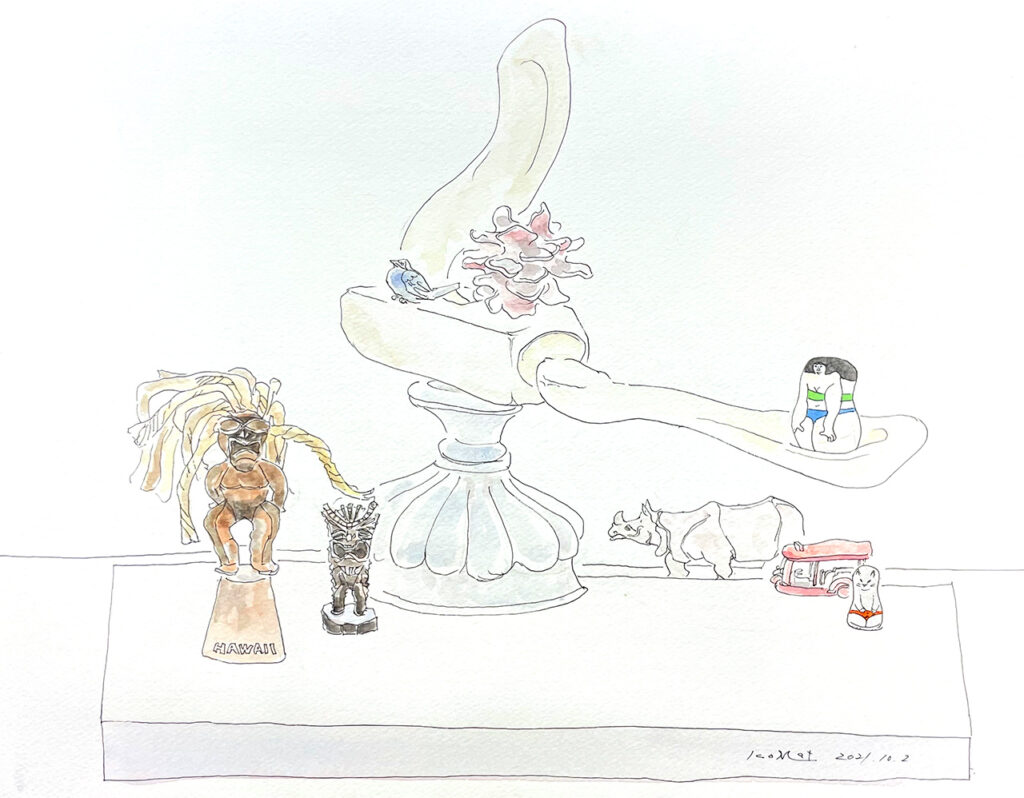
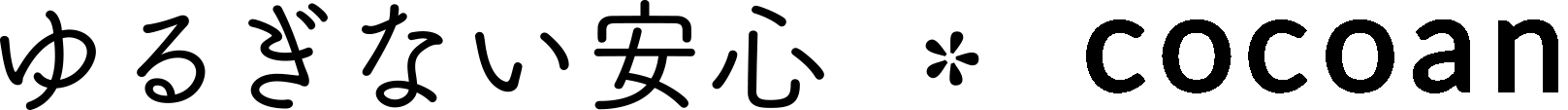


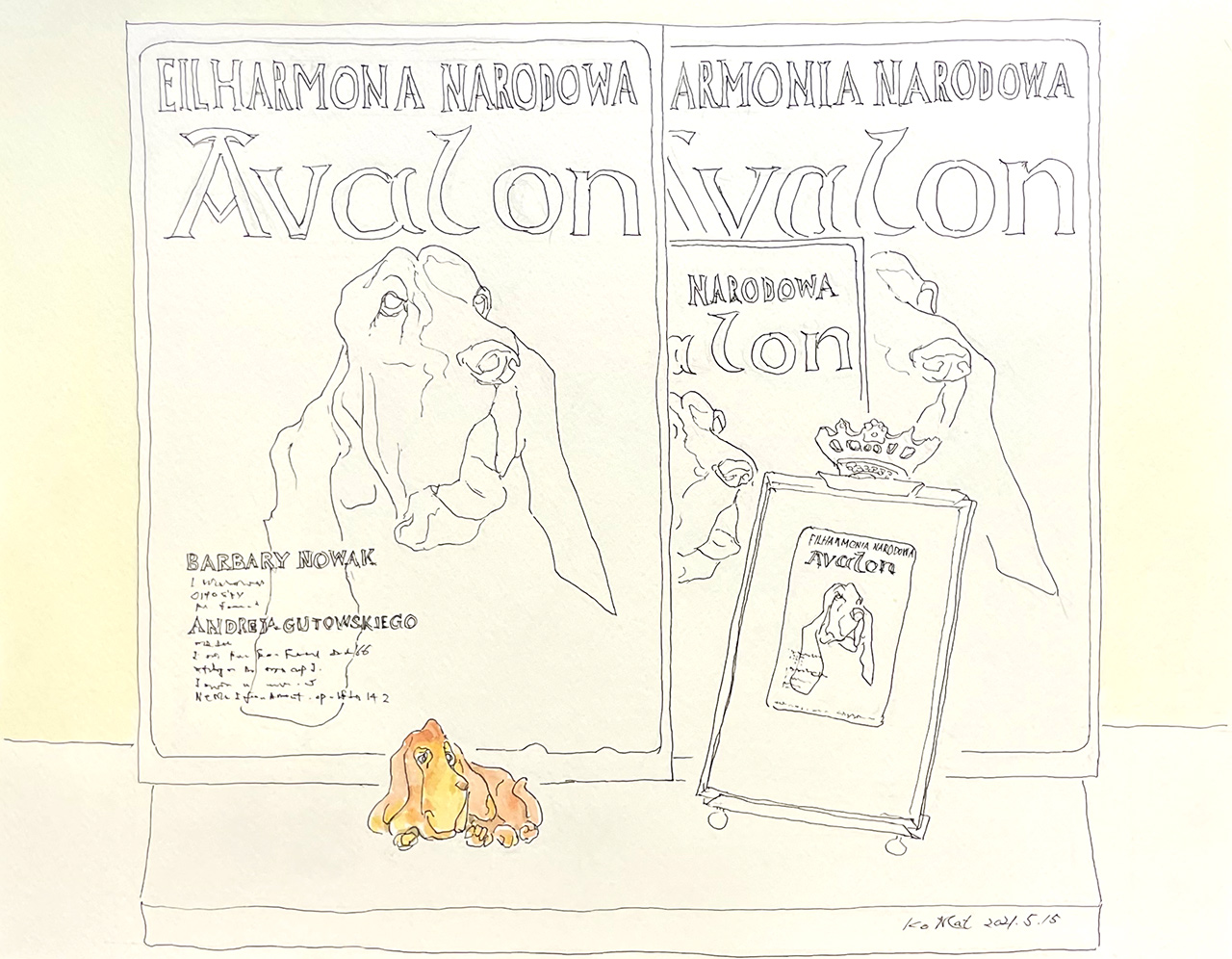



とは_LT.jpg)