HSPと薬の付きあい方

薬への抵抗感
この記事は、薬を飲むことに抵抗のある方にご覧いただきたいです。
HSP概念に関心のある方は、薬への捉え方も細やかです。
クリニックへいらっしゃる方は、基本的にお薬を飲まれています。
私が勤務するクリニックの方針として「薬に頼らない」があげられます。
それは「まったく薬を使わない」ことではなく、必要なときには必要な薬を取り入れる姿勢の表れです。
診断や薬の処方は医師の仕事です。
対症療法も時に必要な過程
対症療法(表面的な症状をまずは抑える方法)は直接的に根本解決できませんが、本来やるべきこと、やりたいことを遂行するためには必要不可欠な過程です。
薬を服用することは、副作用が伴います。
特定の症状が抑えられるだけでいいのに、他の症状が出てくる。
そんな副作用のことを考えて薬を飲むことに抵抗を示す方が大半です。
なぜなら、薬の効果や体感もひといちばい感じるからです。
もしくは以前、薬の服用後、つらい経験をしたことがあるからです。
実際に服用してみないと、効果が出ているのか、どのくらい効き目があるかの実感を味わうことができません。
その不確実性が抵抗感として出てくるのだとも考えます。
クリニック初回診療では、薬に対する認知や捉え方を共有しています。
その内容を心理士・医師へも共有し、具体的な相談や判断を医師へ委ねる、そんな横の連携を密にしています。
抵抗感の仕組みや流れは、人それぞれです。
薬に対する認知が明らかになれば、今の体調や状況に合わせた正しい対処法を見つけることにつながります。
HSP外来薬服用の現在
臨床件数ベースですが、HSP外来診療の方の約8割のクライエントは、睡眠薬・抗不安薬を服用しています。
職場での人間関係、タスク過多、役職・役割へのストレスから、睡眠が取れなくなり、常に不安がつきまとっていく。そんな方が大半です。
残り2割のクライエントは、別の薬を服用されている方、薬物療法以外の対処をしている方となります。
対症療法の視点のみで話を進めると、薬を飲むことが前提という認識になってしまいます。
認知の偏りを避けるために、不安や不眠の仕組みについて、脳神経の視点から話すようにしています。
詳しくはこちらの記事で書いています。
「HSP外来」今後の展望
https://note.com/ugajin_ryo/n/nab71ac8b379b
HSP外来でのスタンスにもつながりますが、不安や不眠を避けるためではなく、根本から不安が出なくなる状態に、結果、眠りにつける状態にするために、薬の力を借りると考えます。
不安も不眠も、理由があって出てきてくれている。
症状や痛みは「何かを伝えようとしてくれるアラート」であると捉えていきます。
薬の捉え方アップデート
感受性の高いと自覚している方へ伝えたいこと──それは、薬を「お守り・味方」と捉えていくことの大切さです。
「薬に頼らない」というコンセプトは、まったく薬を使わないということとイコールではありません。
今の自分のフェーズを知った上で、必要ならば薬の力も活用する視点を持てるかが重要です。
薬を服用することに対して、自分が納得できるか、その捉え方でしっくりくるかを指標に、対話を進めます。
納得できるためには、今の自分の状況を自覚することから始めます。
今いる環境の状況・気候・体調・人間関係・タスク量などを把握する。
現在地を事実ベースで把握することで、余分な行動をせずに済みます。
医者の言いなりにはならない
薬の量や頻度については医師への相談になりますが、言いなりになることなく「自分は今この状況なので、これくらいの薬量で考えてみたい」と主張できるようになります。
cocoanやHSP外来では、自分の身に起きていることや意見・気持ちを伝えるためのトレーニングも実施しています。
自分の状況を正確に把握し、相手に伝えられなければ、自分に合った処方になりません。
薬は今の自分を守ってくれるお守り。
いま起きている問題を自分一人だけで解決しようとしなくていいのです。
活用できるものはすべて活用する。
また、最終的に薬の力を借りることなく過ごしたいのならば、カウンセリングでの変化をみながら、断薬への道のりを医師と相談することになります。
HSP✖️薬という視点で対話できる環境は、おそらくHSP外来だけであると考えています。
cocoanでは、クリニック臨床とチーム医療連携の経験とデータをもとに、これからも提案をしていきます。
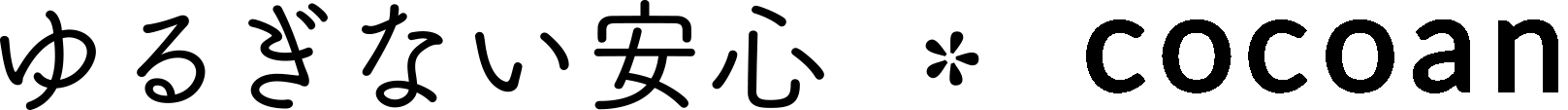




とは_01_LT.jpg)

