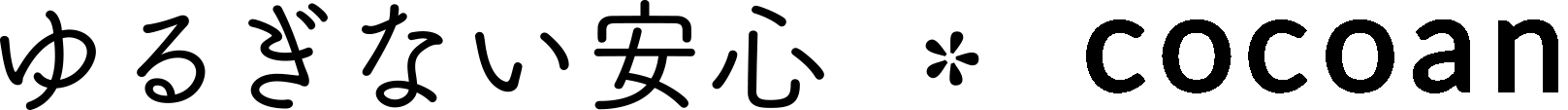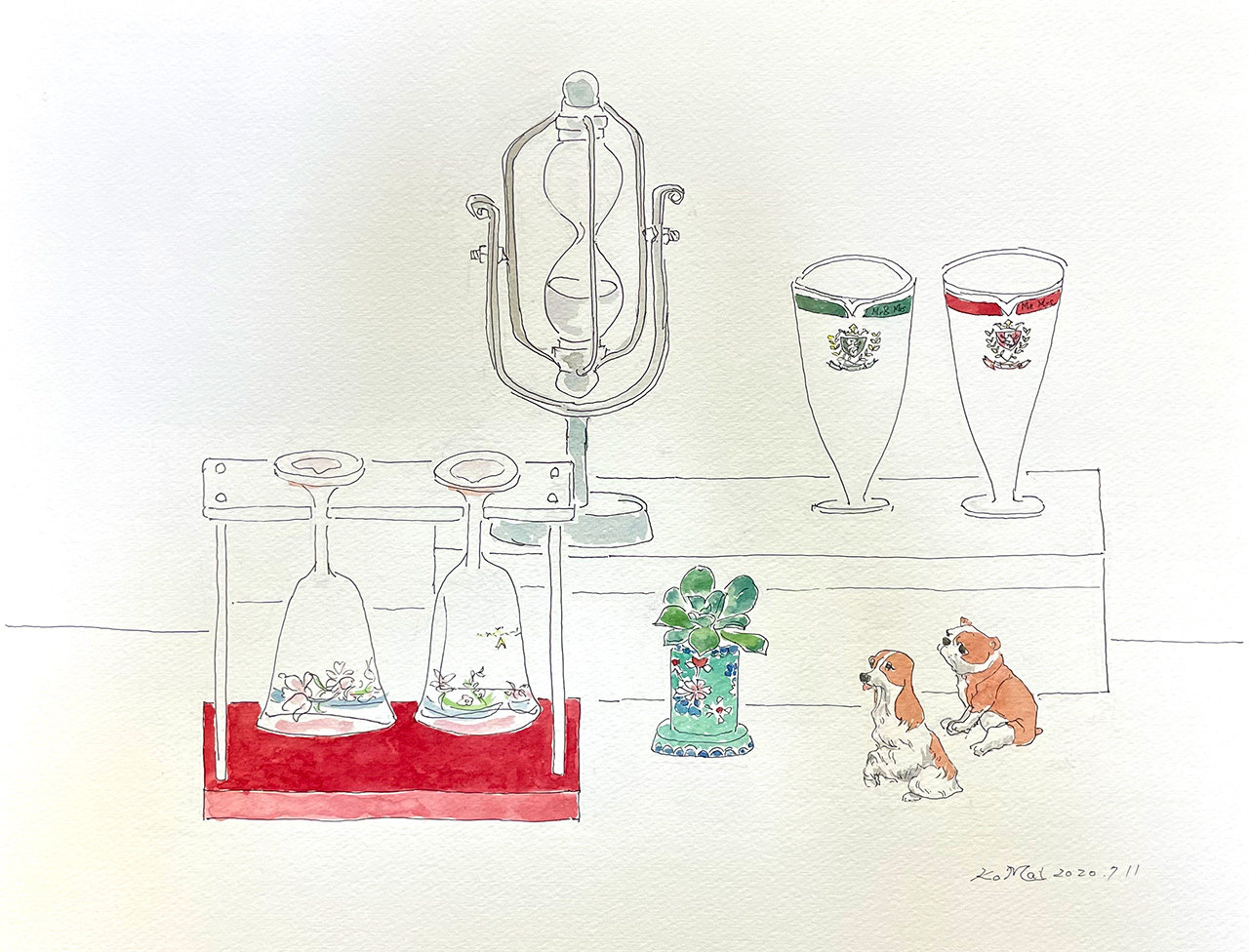3つの環境感受性尺度

HSP概念の現在の研究は「環境感受性理論」をベースにしています。
感受性のちがいを認識しやすくするための視点として、
- 美的感受性
- 易興奮性
- 低感覚閾
という「3つの環境感受性尺度」を紹介します。
美的感受性
ポジティブな感受性というイメージになります。
最近の感受性研究では「ヴァンテージ感受性」ともいわれています。
ポジティブな経験や周囲からのサポートを受けることで、パフォーマンスが向上していくと考えます。
目の前の自然や風景を美しく感じる、自分の趣味に没頭している、芸術・映画・音楽などに触れると感動したり、ワクワクしたりする感覚を指します。
HSP概念が日本で広がり始めた時には、ネガティブなイメージばかり伝えられたため、ごっそり抜けている視点となります。
日々しんどいことがありすぎて、できること、ポジティブな要素を忘れてしまっている状態ともいえます。
ポジティブな一面を実感するためには、心身ともにゆるまっている、安心感を感じられる状態である必要があります。
情報やストレス過多な現代社会においては、美的感受性を忘れないように定期的に味わう機会が大切です。
例えば、
- 朝起きてカーテンを開けたときの陽射しを目一杯あびる
- 味噌汁の湯気を眺め、お椀を両手で包むようにもって暖かさを感じる
- マフラーや手袋に包まれて、あったかい感覚を得る
- 趣味に没頭して、楽しい気持ちを実感する
- 映画や小説などをみて、主人公の気持ちになって浸る
- ワクワクや感動の気持ちを味わいに出かける
例を上げたらキリがないですが、本来もっている美的感受性を思い出すアクティビティを増やしていきましょう。
易興奮性
文字のとおり「興奮しやすい」指標を指します。
「圧倒されやすさ」の尺度になります。
感受性を神経の動きから理解しやすくなる尺度です。
神経には「これ以上、刺激を受けるとムリ」という限界点があります。
易興奮性が起こるのは、その限界点が低いからなのです。
周りは圧倒されずにふつうに仕事をしていて、自分だけが気になって集中できなくなる。
それは神経の限界点のちがいからきます。
周りにとっては限界より低い刺激量でも、自分にとっては限界点を超えた刺激量になっているということです。
易興奮性は、疲れやすさの原因のひとつにもなります。
肉体労働によって疲労する「肉体疲労」ではなく、脳や神経がすり減って疲れる「感覚疲労」によるものです。
室内で作業をしているだけなのに疲れを感じるのであれば、神経を使いすぎて疲労している証拠です。
誰しも使いすぎたら疲れてしまいますが、限界点が低い人にとっては、その頻度が多くなります。
そもそもの刺激耐性量が少ないことと、頻度が多いために圧倒される──この2つが易興奮性として現れます。
対策としては、刺激耐性をつけることと、圧倒されないようにすることの2つになっていきます。
自分にとっては、どの刺激量になったら圧倒されるのか。それを自覚していきましょう。
低感覚閾
「低い感覚の閾値」という意味です。
他の人がまったく気にも留めないくらい小さな刺激も受け取って処理をしていく、ということです。
五感の鋭さを例にすることが多いです。
目の前の風景や場面、音、匂い/香り、味、触覚、温度感、雰囲気や態度、直感などが挙げられます。
これらのどの感覚をとくに察知するのかを伺いますが、人によってさまざまです。
自分にとっては気になることが「あたり前」ですが、これが「あたり前でない」と気づく視点になります。
- 外で鳴りひびく工事の音や振動
- 上の階の人の足音
- 電車内で起こるイヤホンからの音漏れや新聞をめくる音
- 職場でひびく他人の会話や印刷音
- 排気ガスやきつい香水の匂い
- コンビニ弁当などに入る化学物質の味
- 急激な温度変化/湿度気圧変動
- 相手がピリついている様子
- 暴力的/炎上ニュースや場面など
こちらも上げたらキリがありませんが、どの場面でどれほど刺激として受け取っているかがわかると、周囲と比較して些細な刺激を受け取っているのだと推察することができるようになります。
自分と相手の「受け取り方と度合いがちがう」と気づくことからがスタートです。
───────────────
参考:日本における感受性の研究
パーソナリティ研究の動向と今後の展望
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/60/0/60_69/_article/-char/ja/
繊細な子どもの情緒的発達は良い学校環境から良い影響を受けやすい
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400165881.pdf
環境感受性についてのQ&A(Q6に記載)
https://www.japansensitivityresearch.com/q-a-about-sensitivity
───────────────