適職の見つけ方:HSS編

刺激希求性尺度が高い人は、自分から刺激過多にしてしまうという特徴があります。
そのことに気づき、対策していくことで、結果的に適した仕事が見つけやすくなります。
自分がどれだけ意識して対策しても、刺激過多になってしまう環境は、長期的にみてもつづかないということになります。
具体的にどう意識したらいいかについて、お伝えしていきます。
メリハリをつけられる環境に
仕事するときは仕事する、休むときは休む。
そのメリハリをつけられる状況をつくるということです。
周囲がメリハリなく仕事をつづけているとしたら、自分もおなじように仕事をしてしまいます。
自分から休むことを決める必要があります。
また、頭では「大丈夫」だと思っても、カラダがだるかったりした場合は「大丈夫だと頭では思うけど、休んでおこう」と判断できるようにすることが大切です。
周囲に流されずに、自分の状態や体調を自覚できるトレーニングが必要となります。
過去や未来と比較しない
cocoanやクリニックにいらっしゃる、感受性と刺激希求性のどちらも高い方との対話では「気づいたら周囲とおなじペースでやっています」という話題になることが多いです。
ペースを合わせることが“できてしまう”ので、自然とムリをしてしまい、カラダが動かなくなっていきます。
また「過去の自分と比較する」ことで、メリハリがつきづらくなります。
- 先週はできたのだから今もできるはずだ!
- 1回できたのだから、できないなんてあり得ない!
- 周りには「できる自分」でまかり通っているから、できないなんて弱音は吐けない。
などと、自分を縛っていくケースも多いです。
自分の負担度合いや体調を無視している状態になっています。
できる/できないという視点が混ざってしまうために、仕事と休息の区別がつかなくなっていくのです。
過去や未来と比較することなく、「今」の自分がどうなのか? を見つけつづける実践を積み重ねていきましょう。
クリエイティブさを発揮できる条件を明確にする
刺激希求性の中で、新奇な経験を積極的に求める人は、新しいものを生み出す力がつよいです。
ただし、創造力(クリエイティブさ)が発揮されるには“ゆるんでいる状態”が必須です。
例えば、ふと散歩しているとき、ぼーっとしている時、お風呂に入っている時など。
ゆるんだ時にアイデアが浮かんだり、大切にしている言葉が出てきたりします。
それとおなじで、いかにゆるんでいる状態でいられるかで、クリエイティブさの発揮頻度が大きく変わります。
ゆるんでいるとき、集中して目の前のことに取り組めているときの環境
と、
刺激過多のとき、体調が思わしくないとき、疲れ果てているときの環境
とのちがいを言葉にしていきます。
その差を言葉を通して認識をしていくと「これ以上、刺激を受け取ったら、力んでしまっているのだな」と気づけるようになります。
今いる環境において、気づいたら刺激を求めてしまって疲れ果てているとしたら「それは本当に今の自分に必要なことなのか? 無理はしていないか?」と考えるきっかけにしましょう。
力みが出る瞬間を把握しておく
渦中に気づけるようになるためには「どの瞬間に力んでいるのかが分かっている」ことが活きてきます。
適職を考えるにあたって、ひと息がつけるかどうか、力みを定期的に緩められるかどうか、が大きな指標になっていきます。
なぜなら、それがあるかないかで、クリエイティブさが発揮できるか否かが大きく変わるからです。
業種によっては、自分のペースで仕事しやすいものがあるとは思いますが、結局は「どんな環境か、自分がどう活かすか」次第です。
転職に関する面談をする際は、自分が本来のクリエイティブさを発揮できる環境が得られるか? 具体的にイメージできるような質問をすると良いでしょう。
反応検証のための60点提出
- ついついやりすぎて疲れ果てる。
- 後々振り返ると毎度のようにやりすぎていたと後悔することが多いです。
こういう方は、自分でやりすぎを防止できる策をいくつか持っておくことが有効となります。
とはいえ、気づいたらやりすぎてしまうので、中々自分で気づくのは難しいでしょう。
そんな時には「自分にとっての60点で一旦、提出する」ことをお勧めします。
やりすぎて疲れ果てるということは、つねに自分にとっての100点をめざしていると言うことです。
手を抜いている感があるかもしれないですが、6割のパフォーマンスで実行した時に“相手の反応はどうかを検証する”気持ちで臨むと取り組みやすくなります。
追求レベルの差分に注目する
今いる環境で求められているレベルと、自分が納得できるレベルに差がある場合、その差分を把握できるとエネルギー消費を抑えることにつながります。
これは手を抜くということではなく、的確に相手のニーズに応え、効率性が上がる要素だと考えることができます。
やりすぎを防止するためには、自分にとっての限界点よりも前に区切るという実践が必須です。
自分のあたり前や前提は中々自分で気づけないので「6割をめざす」をひとつの指標としてみてはいかがでしょうか。
環境に合わせて、自分が発揮するエネルギー量を調節できるようになると、どんな環境でも仕事がしやすくなっていきます。
ミスや抜けが出るタスク量を知る
普段ならミスをしないことでも、ミスをしてしまう時がある。
そうであれば、そこにミスをしてしまう事情や条件があるということです。
それを明確にしておくことが大切です。
ミスをしないためには、条件が発動しなければ良いのです。
例えば、ミスをした時に、納期が迫るタスクを3つ抱えていたとします。
その状況を振り返ったときは、タスクに追われていて、いつもならできているダブルチェックやリスト作成ができていなかったと気づきます。
いつもなら確認作業が冷静にできているので、漏れがなかったのですが、確認の時間ができなかったことで、結果的に抜けてしまうミスにつながってしまったとわかります。
このように、ミスをするのには必ず理由があります。
そこを認識できることからスタートです。
ミスの条件を把握すれば回避可能
刺激希求の高い人は、元来、いま必要のない刺激まで、自分から求めていきます。
自分のキャパシティをいっぱいにしてしまうので、ミスにつながります。
いま必要な刺激に気づき、それだけに労力を使うことを意識すれば、結果的にミスが減っていきます。
ミスをしづらい仕事もあるかもしれませんが、それよりもミスする条件を知った上で、それを避けられる自分でいましょう。
ミスする条件がわかれば、職を探すときも大きな指標になっていきます。
「あ、この環境や人の考え方は、自分のミスを誘発するな」と感じたら、他の環境を選ぶようにしましょう。
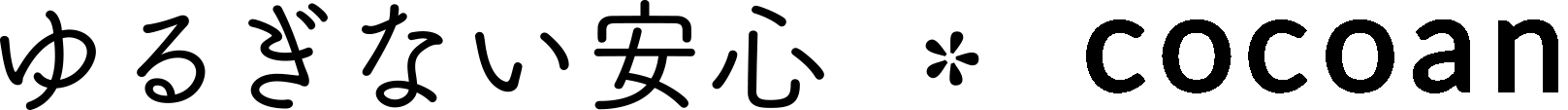


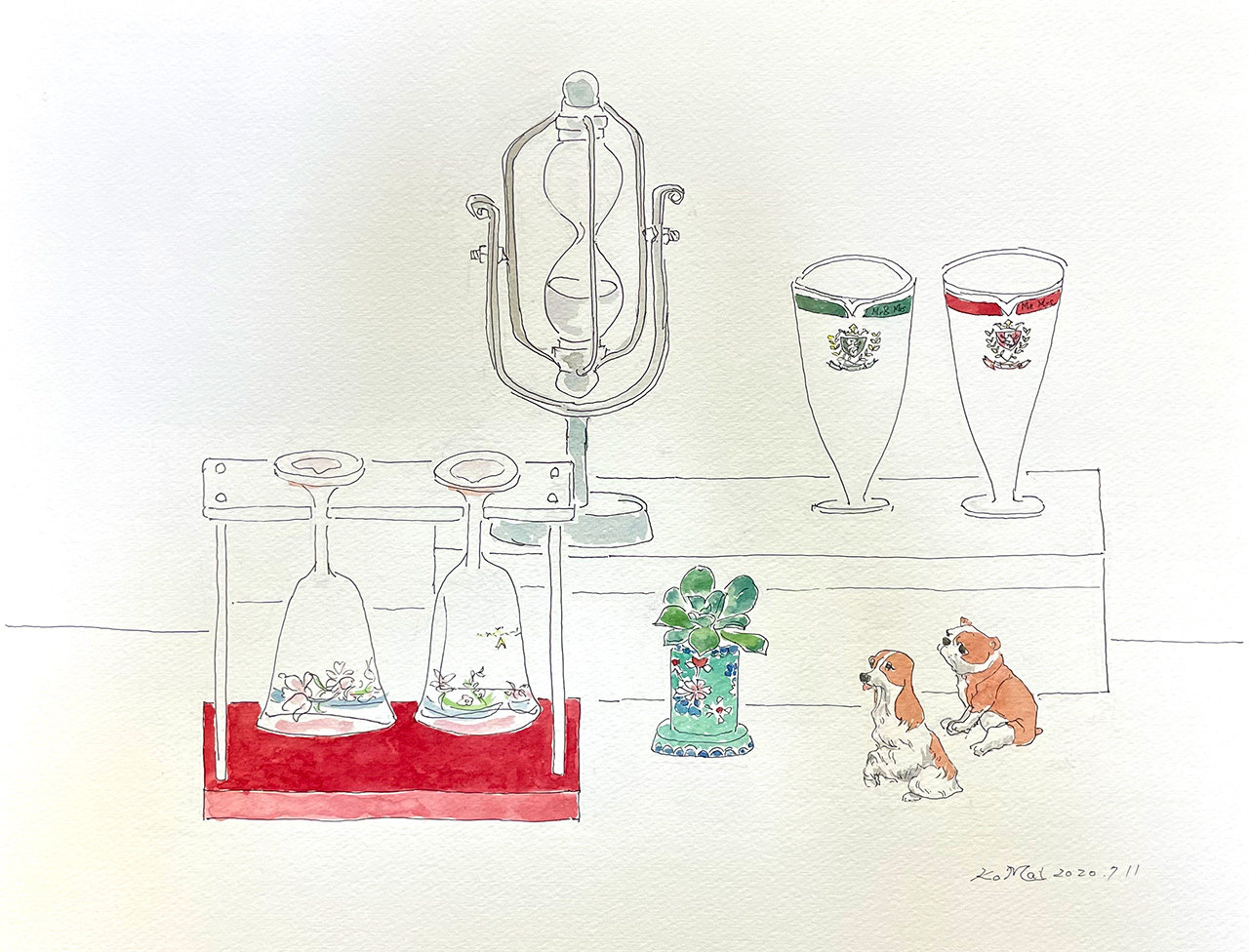
とは_LT.jpg)