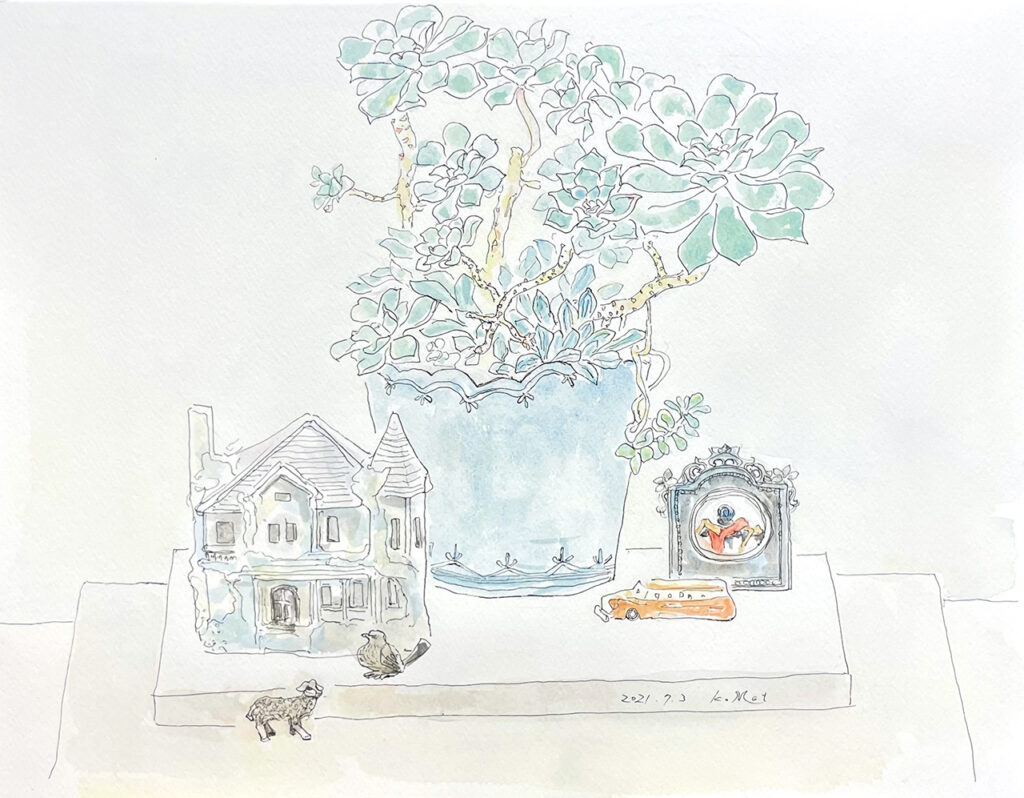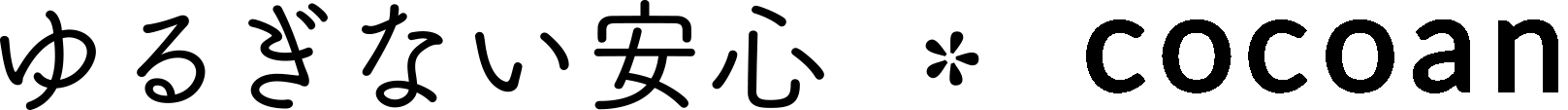現職における生存戦略
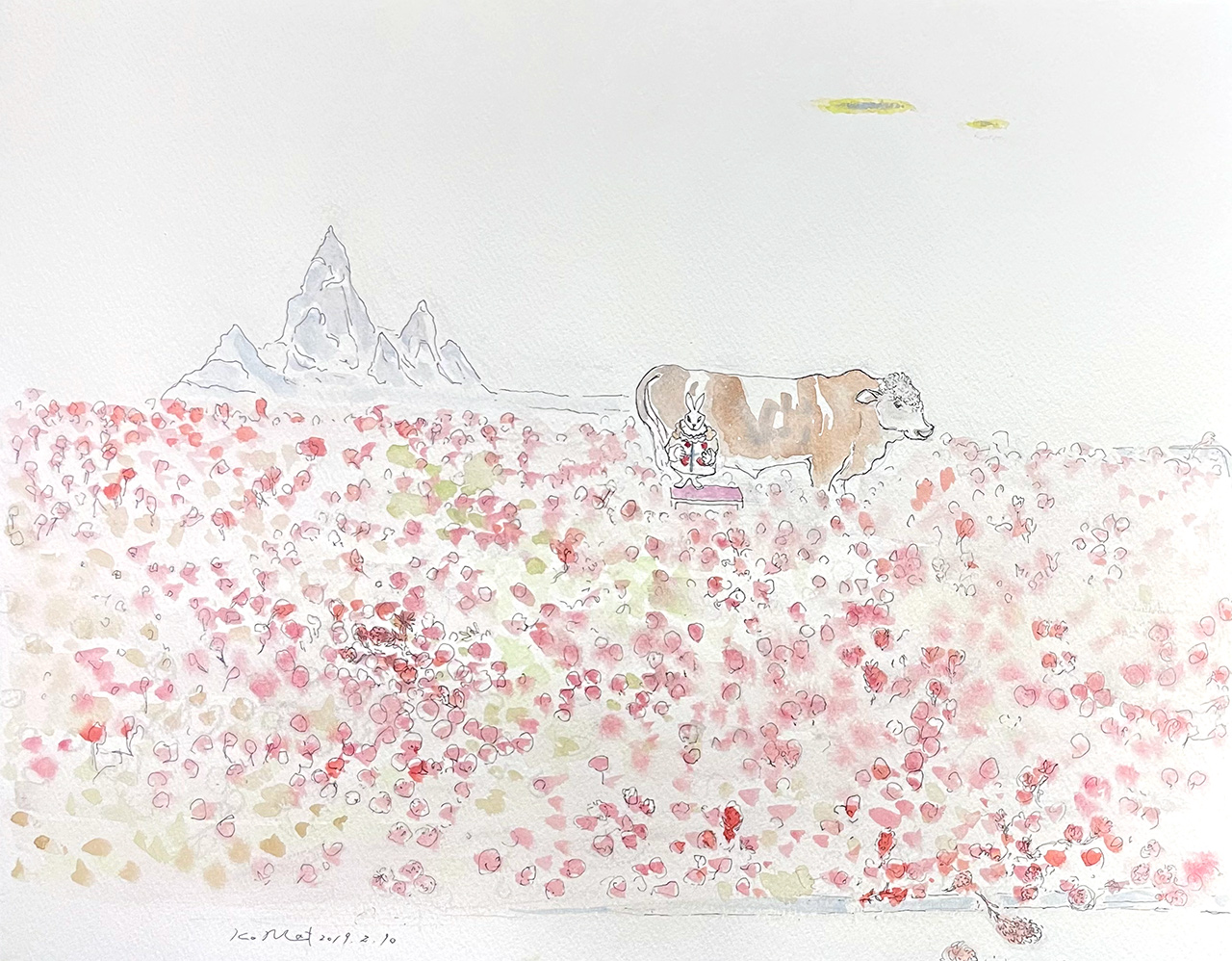
逃げの退職・転職・休職
しんどすぎて、今すぐにでも辞めたい、環境から離れたい、と訴える人がいます。
でも現実を考えると、
- お金を稼がないといけない
- 年齢的に転職はむずかしい
- 転職をしたことがなくて不安
- 他のところでは上手くいかないだろう
と考える。
頭で考えることとカラダから発動する欲求のギャップが大きくなって、悩みになります。
そんな悩みが「逃げの退職・転職・休職」につながります。
確かに、環境を変えることで問題が解決することもあります。
しかし、それがすべてではないです。
また現実問題として、そう簡単に環境を変えることはできません。
だからこそ、いまいる環境のなかで、どう適応し、心地よく過ごせるか?──その術を身につけることも大切な視点になります。
5割が再休職をする理由
厚生労働省の研究班の調査によると、うつ病で休職した社員のうち、5年以内に再発・再休職する割合は、47.1%となっています。
また、うつ病の再発率は60%もあり、その後、再発を繰り返すとさらに再発率が高くなるとされています。
※引用文献(厚生労働省のデータ)
https://kokoro.mhlw.go.jp/return/return-worker/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/hojokin/dl/28_14010101-02.pdf
上記データは、うつ病に限ったデータとなります。
他の症状を含めたら、さらに多くなることは想像に難くないでしょう。
再休職をうながす「神経ループ」
一度休職した人が、再度休職になる理由の大きな視点のひとつに「神経」の問題があります。
具体的には「交感神経がずっと高止まっている状況」ということができます。
交感神経は「闘争・逃走モード」を司ります。
やることに追われている、慣れないことで緊張している、人前で話すこと自体が苦手、など挙げたら枚挙にいとまがありません。
社会に身を置くなかでは、与えられたものを確実に納期内にこなすことが求められます。
これは「つねに闘争している」ともいえます。
また「いますぐ、ここから離れたい」という気持ちが起こるのは「逃走モード」になっているからです。
逃げなければ、自分の身に危険が及ぶと無意識のうちに察知しているのです。
神経の高止まりに関しては、下記の記事も参考にしていただけます。
神経の高止まりとHSP
https://lifecoredesign.com/cca/high-level-of-nerves/
交感神経系がこれ以上、刺激を受け取れない限界点を迎えると「凍りつきモード」に切り替わります。
うつ症状やパニック症状の原因を神経の視点から見ると「凍りつき神経モード」に切り替わっていて、これも「自分の命を守っている状態」ということになります。
症状が出たら「休まないとな」と気づいて病院に行く。
実際に一定期間、休めばカラダは休まって落ち着いていく。
もう大丈夫! と思って職場に戻ると、また再発する。
それは交感神経の高止まりに対する対処ができていないからです。
イレギュラーなことが起きたり、小さなストレスが溜まって爆発すると、また「凍りつきモード」となり、うつ症状が再発する、という仕組みです。
「逃走モード」と「凍りつきモード」という、交感神経の高止まりループが起きている。
このループが起きないように対策することが大切になります。
症状が出る前に「緊張や力みがつづいているな」と気づき、ゆるめることが対策になっていきます。
生存戦略の要は「社会交流神経」
交感神経の高止まりの頻度が減っていくと、結果的に職場を変えなくても仕事ができるようになっていきます。
そのために必要なことは「安心感」を感じられることです。
具体的にいえば「社会交流神経」が育まれ、心身ともにゆるまる状態でいられることです。
ゆるまるとは「張りっぱなしの糸がゆるまる状態」をイメージすると分かりやすいです。
糸がピンと張っている状態は、切れやすく、また劣化が早いです。
必要なときに張って、それ以外はゆるめる状態にしておくことで、劣化を防ぎ、本来の力を発揮したいときに発揮させることにつながります。
これが「メリハリのある状態」ともいうことができるでしょう。
ずっと緊張させるのではなく、必要なときだけ緊張させて、それ以外はゆるめる。
その状態を目指していくと、どのような環境でも適応しやすくなっていきます。
刺激量を減らす具体策を講じる
とはいっても、環境による影響はとても大きいです。
HSP概念のメイン理論である「環境感受性」は、良くも悪くも環境の影響を受けやすい、としています。
現在の職場において、異動・役割変更・タスク量の断捨離ができるかの可能性について考えておくと良いでしょう。
特定の人や状況、タスク量によって、しんどさを抱いているのであれば、根本から変えてしまうことで解決していきます。
- 周囲のサポートがあれば、自分一人で抱える必要がなくなり楽になる。
- 責任感の強い役職を降りてプレーヤーとして仕事できれば、本来の力を発揮することに集中できる。
- 1つひとつ、ていねいにタスクをこなせれば、心の余裕が生まれて仕事の質が上がる。
こういった対策を取ることができれば、総じて刺激量が減っていき、交感神経系の高止まりの状況を抑えることにつながります。
自分のキャパシティに沿って仕事することにつながり、職場では自他共にWin-Winに働きます。
仕事内容や役職は、なかなか自分ではコントロールできません。
要望を伝えることができても、100%叶うものではありません。
とは言っても、要望を伝えなければ状況は変わっていきません。
要望を通りやすくするためには、自分の意見を伝えられる状態にしていくことが必要となります。
事実のみを伝える「物語の流れ」
自分自身が心地よくいられることがスタートラインとなります。
自分の意見はあるけれど、周りの空気感や相手の威圧感から言うことができないとしたら埋没していきます。
周囲の状況に動じずに自分の意見を伝えるための準備が大切です。
具体的には「事実のみを伝える」ことを意識するということです。
感情をぶつけると、相手はまっすぐに受け取ることができません。
相手に伝わるように「物語の流れ」を踏まえながら言葉にしていきます。
下記は、その例です。
『私がチームリーダーになってから、自分の仕事だけでなく、部下3人のタスク管理や教育・サポートの仕事が増えました。
自分の仕事だけでも約1時間の残業をしないと回りません。
それにプラスしてリーダーの業務をしなければならず、疲れ果ててしまいました。
やらないといけないとはわかっていても、カラダがついていかず、睡眠時間も7時間から4時間に減りました。
ご飯がおいしく食べられなくなり、休みのときにも、仕事のことを考えてしまって、気持ちも休まりません。
チームリーダーとしての役割を担うことが、私にとってキャパシティを大きく越えることだと気づきました。
要望は、自分の仕事量を減らす(分配する)か、リーダーの役職を降りて、プレーヤーに専念することです』
いかがでしょうか。
感受性の高い上司であれば「言わずとも察してくれる可能性」はあります。
でも、ほとんどの場合は、言葉で伝えないと認識してもらえません。
感情をぶつけるのではなく、上にご紹介したように、淡々と事実を時系列で述べていくことで、スムーズに要望まで伝えやすくなります。
環境を変えたいけれど、なかなかできない──そんなとき、現職で生き残っていくうえで大切にしたい視点をお伝えしました。
参考にしていただけると幸いです。